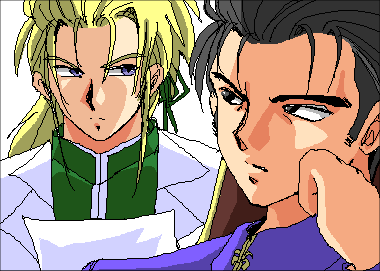
ハッハッハッハッハッハッハッハッハッ…!
刃の様な三日月の下、息を切らしながら、一人の男性が走っていた。
上司と安月給の愚痴を肴に、同僚たちと郊外の呑み屋で飲んで、ちょっと酔い覚ましにふら付いていただけだ。
なぜ自分がこんな目に逢わなければならない?そんな問いが、走る事で血の中を酒気が駆け巡って、思考もままならないままに湧き上がる。
もし捕まれば………その恐怖とともに突如として抑えの利かなくなった胃の中身を道端にぶちまけ、彼の足が止まる。
荒い呼吸を繰り返しながら、吐き気とは別種の悪寒を感じた彼に、弱く寒々しい月光を浴びたモノが振り下ろされ
死神の鎌のような月に向かって、紅い華が咲いた。
数日後〜金閣寺〜
一人の男性が玉座に座っていた。
後ろに撫でつけた髪の似合う端正な顔立ちをしており、
身に纏う紫を基調にした簡素ながらも気品を漂わせる服装と堂々たる雰囲気が、その席を大げさな物としないだけの風格を彼に持たせていた。
大日本帝国三代将軍足利溥義
今日も今日とて政務に励む彼の手元には、各所から届けられた報告書を始めとする書類が握られている。
部下の手によって整えられ、選別されているとは言え、その数たるや膨大であり、
その書類を淀みなく迅速に、かつ見落としなく読み進め、必要とあらば、傍らに控える側近に指示を伝える。
見ている方が目を回しそうな速度でそれらの作業をこなす溥義は、それだけで非凡さの証明を成していると言えよう。
と、一枚の報告書に差し掛かった時、今まで止まる事の無かった溥義の動きが止まる。
そのまましばらく、考えを巡らせた後、自身の右腕と言っていい男を呼び出し、次の報告書に取り掛かった。
数分後、御前に一人の剣士が参じていた。
長く滑らかな金髪を束ねた精悍な顔つきをした男性である。透き通るような青い目に、確かな意志の光が宿っている。
溥義禁衛隊筆頭シンエモン
溥義にとって、最強の臣であり、師であり、友であり最も信を置く漢である。
その男を呼び出すとは何事であるか?自らの君の発する只ならぬ空気と合わせ、溥義の傍に仕える側近達に緊張が走る。
シンエモン 「上様、一体何事でありましょうか?」
その質問に対して、溥義は一枚の書類を差し出す
溥義 「多慧山のレオンハルトからの報告書だ」
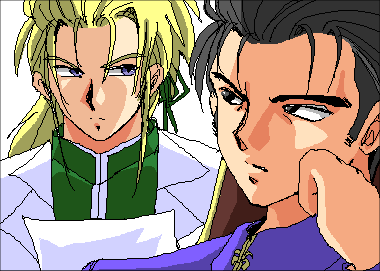
報告書を受け取りながら、シンエモンは内心で眉を潜める
多慧山
多数の山々からなる連山であり、古くは鬼と呼ばれる怪物達の住処とされ恐れられていた場所である。
が、今より二百年前に、当時一豪族であった足利家を含む有力者たちの連合軍によって滅ぼされ、以後大型の野生生物が住処としているが、
フェンスで仕切られた危険区に踏み入らない限り獣が下りてくることも無く、またその獣達自体が、縄張りを侵すものを排除するため、
野盗の類が拠を構える事も無く、極小さな立ち入り可能区を除き、人の手が入る事も無く現代に至るまでその山領を残し、ほぼ大きな事件の無い土地である。
今回の監側所設置の視察、監督のためというレオンハルトの派遣も、
禁衛隊発足から四年たち、その存在が抑止力として機能し始めた、端的にいえば暇ができ始めた事もあり、
普段禁衛隊として、娘と過ごせない彼に対する特例の、半ば休暇に近いものであった。
一体何が?と思いつつ、報告書の中身を見たシンエモンは、その中の記述に目を見開く。
シンエモン 「上様、これは………」
溥義 「うむ、その惨殺事件、報告書にある通り獣の仕業とは思えん」
ターリブ老 「ではこれは、あの」
溥義 「出陣するぞ!シンエモン供をせい!」
シンエモン 「はっ!」
一体さん外伝
『多慧山鬼譚〜昔々のケセナイキオク〜』
文:駄文下記 イラストレーション:はんぺら
青々と茂る若葉は、風に揺られ、草木の香りとさわさわとした葉摺れの音を届ける。木々は傾き始めた日の光を柔らかく地に落とす。
その山の裾野から、一人の男がその頂を見上げていた。
赤い十字の入った緑の覆面をした巨漢であり、彼の肩にあっても未だ巨大に見える大砲を肩に担いでいた。
溥義禁衛隊四の槍、レオンハルト
彼は山から視線を外すと、今度はその視線を傍らに居る人物へと移す。
桃色の髪をした痩身の男である。名を井冨と言い、近隣で有名な資産家であり、監側所設置の責任者を務める有力者である。
が、彼はそんな肩書とは裏腹にオドオドと視線を彷徨わせ、弱弱しい声で、目の前の巨漢に口を開いた。
井冨 「レオンハルト殿…
ほ、本当に今回の件熊か何かの仕業では無いのか?
被害者は皆山中の危険区近くで見つかったのだし、
唯囲いを超えて縄張りに踏み込んだだけという事も」
そうだそうだ。無駄に事を荒立てずとも、今後は警備を強化すれば。井冨の周囲に控える人間からも賛同の声が上がる。
レオンハルト「獣の仕業で有るとするなら、
所持していた持ち物も衣服も漁られて無いのは妙だ。
それに死体の傷口も、獣の牙や爪とは微妙に違う」
井冨 「ではやはり……グラップラー」
震えて出でたその一言に、ざわざわと恐怖を含んだどよめきがあがる。
そのどよめきを聞きながら、レオンハルトは、先程の通信を思い返していた。
シンエモン 「準備ができ次第、拙者と上様がそちらに向かう」
プロパガンダとしての意味も薄く、得体の知れない何者かが相手のこの場に、何故上様自らが?
しかして彼はその思考を中断し、後方へと視線を向ける、視線の先には、転げるように従属が駆けてきていた。
その一言は、彼に雷鳴のような衝撃を与えた。
従属 「た、大変です!マリーちゃんが山に!」
〜数刻前〜
四人の子供の姿が山中に有った。その内三人は、近辺で有名なガキ大将の厳に、その相方の実、二人の子分の様な存在である優であった。
優 「ね、ねえ止そうよ、危ないよ」
厳 「何言ってんだよ。大丈夫だって、
度胸試しなんざ兄貴達だってやってるけど、何も無かったんだし」
実 「そうそう、臆病者は黙ってなって。代わりも出来たんだし」
優 「で、でもやっぱり……」
そう言って彼らの視線が一人の少女に向けられる。色素の薄いセミロングと、くりっとした瞳の可愛らしい娘である。
マリー 「大丈夫よ、優君、ここで待ってて。ささっと取って来るから」
浮かべた笑顔は柔らかく、見た者の心を解すに十分であろう。が厳の内心は穏やかな物では無かった。
山中に有る大樹の傍にのみ咲く花を摘んでくる。多慧山の麓に住む子供たちの間でいつからか始まった度胸試しである。
その花の咲く位置が年々危険区に近づいている事、去年は仕切りのフェンスギリギリだった事を聞かせ、
臆病者の優と、この少女が怯えている間に、自分が、仕様がないとばかりに二人分を引き受け、この愛らしい少女に尊敬の念を抱かせる。
そんな自身の計画が駄目になってしまう。その焦りと目の前の少女の態度が彼の中の小さな意地を、触発した。
数分後、彼は自分を殴り飛ばしたいほどに後悔していた。案の定花は危険区の中にしか無かった、今回は中止するしか無い。
自分以外の意見が一致したにも拘らず、小さな意地から、木を伝い、フェンスを乗り越え、花を手に入れた。
その時であった、背後から聞こえる警告それと同時に、目の前で大岩の様な何かが動いた。
それが怪物の様な大熊だと気付いた時、悲鳴と共に強張った足が苔に滑った。
厳 「うわあああああああああ!!!!」
大熊の爪が厳の頭があった位置を薙いだのはその直後であった
実 「厳!逃げろ!早く!」
その声で僅かに正気を取り戻した彼は、すぐ近くに有った、大樹の根の隙間に転げるように逃げ込んだ。
しかし、大熊は執念すら感じる執拗さで、丸太の様な前足を突き込み、引きずり出そうとしてくる。
次第にその爪が近くなり、遂に服の裾を掠めた。
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い
すりむいた手足の痛みすら忘れる恐怖と後悔を感じていた彼の耳が、何かが何かにぶつかるような音を聞いた
実は驚愕に支配されていた。あの少女の姿は、確かに見えなかった。逃げていたと言うのならそれも理解できた。
しかし、その姿が今、危険区の中に有り、
熊に対し石を投げつけているのは理解の範疇を超えている。
マリー 「早く!厳君を連れて逃げて!」
投石で意識をそらし、実にそう声をかけた後、すぐさま背を向けて走り出した。
助けなければ死んでしまう。その正義感にも似た想いからの衝動的な行動であった。
しかし、鈍重そうな外見であっても四足の獣である熊に対し、人間が走力で敵うはずも、
まともな舗装もされていない山道を少女の足で駆け抜けられる訳も無く。
木の根に躓き、倒れ込んだその上に、風を巻きながら、鈍く光る爪が、振り上げられた。
熊の前足に比べるとマッチ棒の様に細い少女の体がその一撃を受ければ、待っているのは確実な死。激痛の予感から目を閉じるマリー。
??? 「やめなよ。この子はあの人たちの仲間じゃ無さそうだ」
場違いなほど穏やかな声が響き、体が浮き上がる様な感覚が来たのはその時だった。恐る恐る開けた眼に、黒髪の少年の顔が映る。
成人男子の平均程度の上背に、少年から青年への過渡期と思われる整った顔立ちと翡翠を連想させる緑の瞳から作られる表情は、
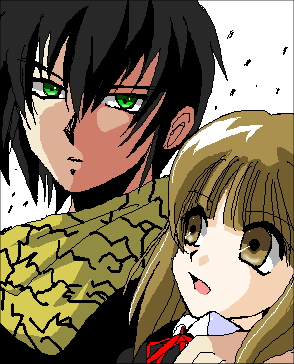
今の状況からすっぽりと切り離された別の何かの様に穏やかであった。
片腕で自分を抱きあげ、もう片方の手を熊の顔に添えて、子供に語りかける様な口調で宥めていたその少年が顔に添えた手を動かすと、
先程まで迸るような殺気を放っていた熊が、嘘のように静まり、鬱蒼と茂る木立へと身を返す。
マリー 「あなたは一体……誰?」
事態について行けず礼より先にこぼれ出たその問いに答えず、マリーの体を丁寧に抱えあげると、
サクサクと草を踏む音を鳴らしながら、あまりの事態に硬直していた厳に近づき同じように抱え、
体重が無いかのような軽やかな跳躍と着地でフェンスを飛び越え、危険区を抜け出し、歩き出した。
実 「お、おいあんたどこに行くんだよ?」
??? 「二人とも怪我をしてるから、
特にこの女の子は早く手当てしたほうが良いみたいだしね」
はんなりと告げられたその言葉に、初めてマリーは足を伝う生温かい流れを自覚する。
転んだ際に何かに引っかけたか、脹脛が切れていた。途端に襲った痛みに思わず呻き声をあげるマリーの姿に、厳も実もとりあえずは口を噤んだ。
木に隠れるように立つ古びた小屋であった。
所々接ぎがあるけど、掃除して有るのか埃っぽくは無いな。
途中に有った小川で傷を洗い、その小屋に入った後、厳が呑気な事を考えている間に、
棚から薬箱を取った彼が腰を下ろし、何やら暗い真緑色の軟膏を取りだしていた。
流石にその色は、痛みを感じ、血を流しながらも少し躊躇うものであった、が
マリー 「えっと……あの………」
??? 「?ああそうか。まだ名乗って無かったね。
僕は至天といってこの近くに住んでいる者だよ」
いや違う。と口に出す前に、脹脛の傷口に軟膏が塗りつけられた。
マリーの持っていたハンカチを熱湯消毒し、当て布代わりに使った後、少し古い包帯が巻かれ、
厳の擦り傷にも別の薬(くすんだ黄土色)が塗られ、とりあえずの手当てが終わった。
至天 「忠告させてもらうけど、二度とあそこには入らないほうがいいよ。
最近何者かが入ってきたせいで、特に殺気立っているし、
そうでなくても人が踏み入るべき場所じゃあ無いからね」
ゆったりと、しかしはっきりと言い切られたその言葉に、反論を返すことはできず、
言葉に詰まる厳たちに、先程と変わらぬ穏やかな顔で振り返り、麓まで送るよ。と声が掛けられる。それを断る理由は彼らには無かった。
麓への道すがら、軟膏で痛みは和らいだものの、未だ無理はしない方が良いと、至天に背負われたまま、ふと気になった事を口にする。
マリー 「至天さんは、どこに住んでるの?」
後ろを歩く厳も実も、この近辺では有名であり、また彼らも、(近辺の住人をどれだけ知っているかで競争していた為)大体の人を知っている。
なのに、この近くに住んでいると言った彼が厳達に知りも知られもしていないのはおかしい。そんな思いから発せられた質問に、彼は何でもない様にに答えた。
至天 「ああ、僕はさっきの小屋よりもう少し山頂に近くに住んでるんだよ」
さらりと発せられたその言葉は、しかしその場にいた全員を驚嘆させるに足る言葉であった。
先程の小屋は、危険区のフェンスのほぼ近くに有り、そこよりも山頂よりという事は、即ち危険区の只中という事である。
厳 「おいおい!人の入っていい所じゃ無いんだろ?良いのかよ、それ?」
至天 「大丈夫だよ。僕は普通の人間じゃ無いからね。
一人で住む分には何の問題も有りはしないよ」
実 「でもさ、態々山ん中いねーでも、町に降りたほうが良いんじゃねーの?」
至天 「良いんだよ、僕は……一人のままで」
強い訳ではない、大きい訳ではない、しかし、その声は、それ以上の追及はしてくれるなよ、という何かを孕んでいた。
その時はたと気づく、背負っている少女の、自分の肩を掴む手に、握り締めるように力がこもっている事に、その小さな体が僅かに震えている事に
マリー 「そんなの………良く…無いよ。一人なんて……良い訳無いよ」
脳裏に浮かぶ映像、安らかな眠りを一瞬で粉々に砕く轟音、悲鳴、怒号、否応なしに伝わる衝撃、当たり前が呆気なく崩され炎の中に消えていく。
訳がわからない、どうなったかがわからない。死を受け入れられず、何度問いかけても何も答えてくれぬ母親
どれだけ泣いても、助けてと叫んでもだれも答えてくれない。誰も来てくれない。
どうして?どうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてドウシテドウシテドウシテドウシテドウシテドウシテ?
ナンデダレモキテクレナイノ?
私一人、ワタシハ…
もしあの時、あの大きく強く、やさしい手で救い上げられなかったら……
その恐怖が知らず体を、声を震わせる。
明らかに変わった空気を感じ、ああ。と気づく。この少女は孤独を知っているのだ。そして他者の痛みを感じられる優しい子なのだ。と
だからこそ…
至天 「一人のほうが良い。君たちや他の人達みたいに、
弱いだけの人達と関わって生きるよりは何倍も」
先程までとは違う反論を許さない、冷たく硬質的な声に全員が気圧され、沈黙が落ちた。
と、
レオンハルト「マリー!返事をしろ。マリー!」
木立に響き渡るその声に、少女の表情に喜びが浮かび叫び返す。
その声の余韻が消え去る前に、彼らの前に緑色の覆面をした大男が現れる。
大男は、至天の背にいるマリーを認めると、まっすぐそっちに向かい始めた。
その太い腕で至天の背からマリーを受け取りながら問う。
レオンハルト「マリー、無事か?この少年は?」
マリー 「うん。大丈夫、至天さんが助けてくれたから」
至天 「一応、釘は刺しておきましたが、
二度と山に入らないようきつく言っておいて下さい。
彼女のお父さんなんでしょう」
娘をその太い腕に抱き、返事を返しながらも、内心には別の疑問が湧き上がっていた。
何だ、この小宇宙は?この男グラップラー…か?
自分の姿を見た瞬間、目の前の少年から僅かに感じた小宇宙、それは今までどんな戦場においても感じた事の無い異質な物であった。
しかしその疑問も、後ろから現れた井冨の一言に思考の隅に追いやられる。
井冨 「レオンハルト殿!ここに。マリーちゃんは見つかったか。本当に…
あイヤその前に、足利溥義様、及びシンエモン様がご到着なさった。
報告のため御帰還してくれるか?」
了解した。と返す間に至天は山中へと踵を返す。その背に向かい父の腕に抱かれたままのマリーが声をかける。
マリー 「あ、その、至天さん……有難う」
言いながら、井冨の私兵に保護されていた厳と実を見るが、二人とも先程の言葉が気になっているのか、不貞腐れたように視線を外す。
しかしマリーに彼らをとがめる事は出来なかった。
何故なら心情的な問題の前に、自らをその腕で抱く父から、確かな怒りを感じたからである。
〜井冨邸〜
帰る道すがらの説教でヘロヘロになった少年達を家に帰し、宿舎にマリーを預けた後
はせ参じたレオンハルトからの報告が終わり、場に一端の静寂が下りた。
溥義 「つまりは、あの山には何が潜んでいても可笑しくないという事か」
井冨 「は、はい。近づけば恐ろしいとは言え、あの山に住む獣達のお陰で
野党の類が拠を構えないものですから、
お互いに不干渉が暗黙の了解になっておりましたので」
シンエモン 「突然変異種も少なからずいると聞く。
確かにそれも間違ってはいなかったのであろうが」
レオンハルト「グラップラーや怪物の様な獣が相手……ともなればな。
やはり我々が直接出向いての山狩りになるか」
役人A 「申し訳ありません。我々だけではあの山には………」
シンエモン 「いやいやお気になさるな。しかしこうなると半蔵不在が痛いですな」
虎の縄張を蹂躙出来る犬は居ない。
その強大な力が抑止力となり、禁衛隊全体での仕事が減った、つまり表立った事件は少なくなったが、水面下での動きは無くなった訳ではない
そう言った情報を探るために、忍びたる半蔵は、その本分においての仕事が増えている状況である。
溥義 「何はともあれ、今宵は準備を整え休め、明朝には動く」
承知。の声とともに、ある者は慌ただしく、ある者は思案気にその場を発っていった。
その晩、明日の準備を終え、寝室に戻るシンエモンの前にレオンハルトが現れた。
レオンハルト「筆頭殿、少しいいか。何故上様がおられる。
こんな得体も知れぬ相手に対し、少し軽率では無いか?」
シンエモン 「……その事か。まあ仕方あるまい、少し付いて来てくれ」
そうして、人気のない場所に移ると、帝国最強の剣士はその口を開いた。
シンエモン 「月形家の名は知っているだろう?」
レオンハルト「二百年ほど前に当時の帝を殺し、
自らが国を乗っ取ろうとした逆賊だろう?
こちらに来てすぐに聞いたが」
シンエモン 「うむ、それに関係が有るのだが」
今より二百年前、多慧山を根城とする鬼達に対し、一大攻勢が仕掛けられた
人ならざる鬼の力は強大であり、毒煙と結界、呪法によって優位に立ち、
グラップラーを含む大戦力を投入してもなお浅からぬ被害を出しながらの、勝利であった。
しかしその数年後、足利家は、当時多慧山の一角を治めていた月形家が滅んだと思われていた鬼の内一体を密かに擁し、
反乱分子を率い帝の殺害を企てている事を突きとめた。
足利家はその黒き野望を打ち砕くため、傘下や和議を結んでいた家たちを率い直ちに兵を送り、
月形家の一族と反乱に関与していた一族を全て殲滅し、その領地隅々まで兵を配備したが時すでに遅く、
討伐から逃れたその鬼にが、一夜の内に山一つと村三つの生き物を殺した後、足利本家を襲撃
援軍として集まっていた他家の者達を惨殺し、その当時の頭首殺害しようとした所を援軍に現れた帝軍によって撃退されるも、
ついぞ死体が見つかる事も無く、多慧山に消えたと言われる。
レオンハルト「つまり、今回の件に件の鬼か
その子孫が関係あるかも知れぬ、という事か」
シンエモン 「ああ、もしそうなら、足利家当主として思う所が有るのだろう」
レオンハルト「それにしても……鬼…か」
その時レオンハルトの脳裏に、あの少年の姿が浮かんでいた。
あの小宇宙の違和感……今まで感じた事の無い物だった……まさか。
ついと視線を上げた男達の眼に月が映る。見慣れたはずのそれが、やけに不吉な物に見えた。
同じ頃、至天は樹木の切れ間から除く月を見上げていた。
アノトキモコンナツキダッタナア
軽く頭を振り思う。返事くらい返すべきだったのに、悪い事をしてしまったな、と。
夜の山中の冷気と相まって寒々とした印象を与えるそれを、薄ぼんやりと再び見上げながら。
だが、足利家の名前を聞いたときに湧き出た、忘れていたはずの感情、知らず積み上げられていた感情。
その二つを気付かないよう、気付かれないようにする事に頭が占拠されていた。
唯でさえ、バイオリズムの関係か今あたりの時期は奴が強くなるのだ。
枝葉が僅かに荒れているのを見つけ、屈み込み、足元を調べる。獣のそれとは違う足跡が、小さな窪みに続いている。
その窪みの中を覗き込み、土を退かす、その先から現れた、真新しい木の枠と、それが被せられたボロボロに古びた子供が屈んでやっと通れるような狭い通路。
良く見つけたものだ、と嘆息する。
周囲の気を探り、何もいないのを確認すると、枠板に手を掛ける、経年劣化していた木材がいとも簡単に崩れ落ちる事を確認し、大きくスタンスを広げ、眼を閉じる、
ミナイフリヲシテイテイイノカ?
深く吸い込んだ息を、全て追い出すように気を吐きながら、突きだされた平手が通路を囲む土に触れると、
濁流の様な音を立てながら、古びた通路は土の中に姿を消した。
セッカクムコウカラアラワレテクレタンダゾ?
崩れ落ちたそれを確認しながら踵を返す。
ナニモセズニ。ウラミヲカカエタママデイイノカ?
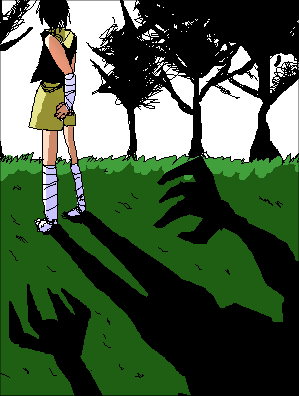
頭の中に浮かぶその声をかき消すように今度は強く頭を振る、何を考えている、どれだけ昔のことだと思っている。
そう言い聞かせ、作業に戻る。声は先程までより淡く、しかし確実に、頭の隅で響いていた
声が響く。消えない声が。忘れて得ぬ声が、暖かな記憶が蘇る。
……燃えていく。切り裂かれていく。そこに有った笑顔も、差しのべられていた手も。何故だ?何故こうなる?
晒し物にされた冷たい躯に投げかけられる侮蔑の言葉、口汚く罵る人人人ひとヒトヒトヒと
違うと叫んでもその声は届かない。
ニクイノダロウ?スベテヲウバッタヤツラガ
クヤシイダロウ?ヤツラガサンビノコトバヲアビルノハ
小さな小さな憎しみがそのドロドロとした体を湧き上がらせ、器を満たしてゆく。
ニクイノナラ、クチオシイノナラ、ツブセ、ツブシテシマエ。ナニヲタメラウコトガアル?
カタキヲウテ、ノウノウトイキルヤツニソノツミヲオシエ、コンドコソチヲトダシテシマエ
コロセコロセコロセコロセコロセコロセコロシテシマエ
悪夢から覚める。開いたその眼に、爛々と光らせて。
翌朝。朝靄と清涼たる空気に包まれた木立の中を駆ける影が有った。
溥義禁衛隊筆頭シンエモンである
足音をたてず、周囲に気を配りながらも、その速度は、そこらの地を駆けるアスリート所か俊足の獣をすらが真っ青になって平身低頭するほどの物である。
グラップラーの能力は瞬発力、持久力、反射神経等において、常人の思考で計れる物では無い。
S級グラップラーともなれば、気配を感知する能力も野生の獣を大きく凌駕する。
その中でも最強に数えられる禁衛隊に属する彼らからすれば造作もない事である。
何者かに対する捜索は早朝から始まった、レオンハルト、シンエモンよる作戦であり、シンエモンは奥の探索を任された。
当初はいかにS級グラップラーとは言え、単独でこの山に入るのは危険と難色を示す者もいたが、事実その捜索作業は早く
さらに野生生物を刺激するのでは、という懸念も、その獣たちがシンエモン達に敵意を持たぬ上、
関わるべきでは無い圧倒的な強者と本能的に判断したため外れていた。
一際大きな樹に飛び移った所で、注意深く周囲を探るが、小宇宙や不審な気配の欠片も無い。
この近くには居らぬか。
更に奥に広がる木々に隠れた薄暗い空間に眼を向けるが、どうにも嫌な予感が拭えない、背筋に得体の知れぬ何かがへばり付いた様な感覚。
しかしそれはこの薄暗く人を拒絶する様な場所に対し抱く不安感の様に漠然とした物であった。そして彼は足場にしていた樹を蹴り、駆けだした。
自らは足手まといになりますからと、山に向かわず、簡易作戦本部となった別宅にて待機していた井冨の耳に何やら騒々しい声が聞こえてきた。
何かと思い門の方を覗き込むと小さな影が四つ守衛に押しとめられていた。
優 「げ、厳君。やっぱり不味いんじゃないかな。直談判なんて」
実 「駄目なんじゃ無いかなぁと思ったけど、やっぱり駄目だったか」
厳 「な事言ったってしょうがねえだろうが!ていうか離せよ!」
守衛 「痛っ、お前脛蹴るんじゃねーよこら」
得体の知れぬ化け物が出没しており、山狩りが行われる。
父親が井冨の私兵として雇われている優からその情報を聞いた厳は、一も二も無く、昨日の少年に忠告して山を降りさせるべきだと主張した。
何かやばい存在がいる以上、自分たちで入るより、誰かに人が住んでいる事を伝えて、何とか頼み込んだ方がまだ現実的だと提案したのは実であった。
ちょうど荷物を届ける用事の有った優と、是非にと頼み込んだマリーを連れて門前まで来たのは良い物の、
何のつてもない子供が意見をしに来たと言って通されるはずがなく。守衛相手の小競り合いはいかにも呆れ顔の井冨が止めに入るまで続いた。
騒動を見かねた井冨に中に入れて貰い、四人はとりあえずの事情の説明をし終える。
井冨 「つまり、君たちを助けてくれたお兄さんが、
山の中に残ってるから保護して欲しい。という訳だな?」
マリー 「すいません。急にこんな事」
いきなり押しかけての要請、幾らなんでも非常識と言えるそれ、もしかしたら禁衛隊員の娘という事で、
気を使わせて仕事の邪魔をしてしまったのでは無いかという思いからの謝罪だったが、井冨はそれに鷹揚に答える。
井冨 「いや、構わんよ。私としてもあまり犠牲者は増えて欲しくないし、
多少手持無沙汰でも有ったしね。確かに伝えよう。
それより喉が乾いたろう?
飲みたまえ、オリジナルジュースだが味は保証するよ」
その言葉と共に、井冨が退室する。
勧められた手元に有る乳白色の飲み物を見る、甘い香りがなかなかに食欲をそそる物であったが、父と至天と名乗った少年が気にかかり飲む気が起きなかった。
厳 「お、飲まねえんだったら貰って良いか?」
一杯目を飲みほし、そう聞いてきた厳に、良いよ。と返すと、喉を鳴らしながら飲みほした。よほど味が気に入ったのであろう。
その後山中にいる父の事を心配する優を励ましていると、軽く装備を整えた井冨が入室する。
その時彼らは互いに向かい合って話していた、故に、部屋に入り空のコップを見た瞬間、
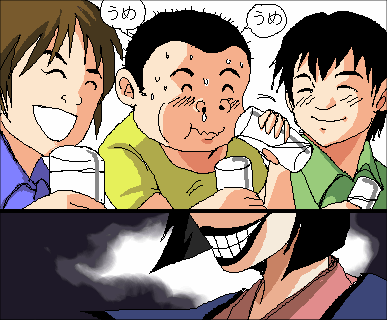
にい。と歪んだ井冨の口元に気付いた者は居なかった
同じ頃、シンエモンよりも浅い位置で探索をしていたレオンハルトは、妙な胸騒ぎと共に、もと来た道を引き返している所であった
しかしその途中異様な気配を感じ、足を止め、周囲に気を張る。
この小宇宙。あの時の………
遮蔽物の多い場所での小回りを考え持ってきたショットガンを構え、気配の方向に向き直る。
その視界に、翡翠の瞳をした昨日の少年が現れる。
レオンハルト「待て、確か至天だったな。ここで何をしている」
至天 「あなたは……退いてださい。あなたに用はないんです」
目つきも身に纏う空気も明らかに昨日とは異質な、攻撃的な物であった。
自然レオンハルトの口調も緊張の交るきつい物となる。
レオンハルト「そうはいかんな、貴様のその小宇宙
今まで人間相手に感じたことの無いものだ
どういう事か説明して貰うぞ」
至天 「お願いだから……退いて下さいって、言ってるでしょぉ!」
途端噴き出すように増大した小宇宙と、その瞳に映る確かな狂気を認めた瞬間レオンハルトは引き金を引いていた
一発目の散弾は、彼の立っていた場所の土を抉り、樹を削り取った。
避けられた、しかしレオンハルトに動揺は無い。すぐさま次の弾を放ち、三発目を装填する。
放射状に広がる散弾は至近距離で無ければ効果は薄い、これはあくまで牽制、本命は熊撃ちに使用されるそれよりさらに大型化した一瑠弾である。
レオンハルト用にカスタマイズされたショットガンから発射されるそれは、特別製の装薬によって易々と音を超える弾速を持ち、
グラップラーと言えど、当たれば唯では済まぬ威力を秘めていた。
とにかく動きを止めて、事情を問いただす。
二発目の発射音と共に飛び上がった至天、空中ならばかわせもすまい。上手く当たれ!
動きを予測し三発目をたたき込んだその時であった。至天が、
舞い散っていた木の葉の一枚を蹴って、空中を動いたのは
馬鹿な!と口に出す間もなく、目の前に降り立った至天の蹴りが、ショットガンを弾き飛ばす。
指の痛みを知覚する前に反射的に放たれた蹴りが至天を直撃し、弾き飛ばす。が、足に伝わった感触は、まるで空振りと錯覚するほど軽い物であった。
中でくるりと回転し、態勢を立て直した至天が、今度は思い切り踏み込む、
左腕に装備したシュツルム・ヴィントを向けるが、発射の前に、疾風の如く速さで間合いが詰められた。
レオンハルト「ベルリンの赤い雨!」
迎撃に繰り出された手刀を、左に弾けるようにかわす。
肩口の服が破け、裂けた皮膚から血が流れ出すが、至天はまるで意にも介さず、レオンハルトと摺れ違い、後方に通り過ぎようとする
逃がさんとばかりに再びシュツルム・ヴィントを向けるが、至天の姿が消える
上か、と思った瞬間頭上に張り出していた枝を蹴った至天の足が地面を踏みぬいた。
外した?と疑問が浮かびながらも反射的に目の前の標的に狙いを定めたその時、レオンハルトの足元が喪失した、
攻撃を繰り出さんと踏みしめていた地面が崩れたのだと理解した時には、唸りを上げながら放たれた蹴りが半ば埋まった脚に食い込んでいた。
レオンハルト『どういう事だ?さっきの動きといい、蹴りの手ごたえといい
まるで体重が無いかのようだがそれに今の掌は…
……いや待て、確か前に半蔵が』
禁衛隊が発足して間もないころ、ハッタリの雷斬の原理を尋ねた事が有った。
ハッタリ 「これかい、えっと確か原理は………ああそうそう、オホン。
良いか半蔵この技は己の中を血と同じく駆ける内氣を形にする物だ。
心を静め、丹田より始まる氣の流れを指の先、
髪の毛の先まで自覚せよ
そしてその流れを全て己が右腕に導くのだ。って爺ちゃんが言ってた」
レオンハルト「氣の流れ、か。筆頭も同じような物を使うが、良く解らん概念だな」
それは、ある種当然とも言える事であろう。
レオンハルトにとって戦う力とは、強固に重さと固さを主張する銃砲であり、鍛え上げた体の持つ力であったし、
小宇宙もそれを示すバロメーターという認識であったのだから。
ハッタリ 「俺も良く解んないんだよね、
雷斬りもやってる内になんとなく出来たって感じだし、
唯爺ちゃんの話では、自分自身の内氣と、
自然界の其処かしこに有る外氣って言うのを干渉させて
体重を無くすほどの反発力を作ったり、
軽く触るだけで地面を崩したり出来る連中もいるってさ。
そうそう思い出した、確か流派名は………」
もはや魔法だな、と零した言葉も聞こえていないようにうんうんと唸る半蔵が、がばっと顔を上げる。
レオンハルト『森羅合一錬氣術!』
先程の流れ弾で折れた木が倒れる音が消え、レオンハルトが足を引き抜いた時には、至天はすでに山の入り口に向かって駆けだしていた。
それが踊るように彼らの前に現れたのは、先程から聞こえていた轟音に、近衛兵と井冨の私兵が集まり、陣形を形取り始めた頃であった。
突如現れた少年を制止しようと声をかけた数人があっさりと気絶させられる。
一人が慌てながらも吹いた笛の音が響いた後、数人が構えたサブマシンガンから放たれた銃弾は、その役目を、草や木、地面に向かって果たした。
彼らとて訓練された人間である。
サブマシンガンで弾膜を張りつつ小銃を持った者が狙い撃ちながら溥義を護るように少年と溥儀との間に割って入り、
笛の音を聞いた禁衛隊の戻るまでの時間を稼ぐ、必要とあれば八人がかりで運んできた大型徹甲砲も使う。
その考えは得体の知れぬ相手に対しては、まあ妥当な判断であろう。
しかし、目の前の者の速度はそれを許さず、厚くなりきっていなかった弾膜を突っ切り、
その右腕に握られた石造りの小刀を今まさに溥儀の喉元に突き立てんと肉薄した。
ドバァッ!
暁光を束ねたような金色の髪の剣士の一閃が放たれたのはその瞬間であった。
攻撃に意識を奪われていたがゆえに回避が遅れた至天は、右肩を深々と切り裂かれ、後ろに飛ぶも態勢を立て直すことも出来ず、地面を転がった。
シンエモン 「上様、お怪我は有りませぬか?」
溥儀 「問題無い、それよりシンエモン」
シンエモン 「解っております」
そう言って剣士が振り返った方向、兵たちが銃を構えながら様子を窺っていた至天が跳ね起きる、
切り裂かれ時間差で足元に落ちた右腕から大量の血を流しながらも、その眼に映る敵意は一欠けらも陰ってはいなかった。
至天 「なんで………」
ダカライッタダロウ
言葉を発した至天に対し三度銃声が轟き、その体が大きく傾ぐ、
奥から銃を拾いなおし、未だ紫煙の昇るそれを構えたレオンハルトが現れ挟み打ちの形になった。兵士たちに自然安堵が広まる。
こいつが何物かは知らんが、手負いの上にS級グラップラー二人による挟撃状態、この戦いここで終る。と。
しかし、
至天 「僕は…こんなもの……」
ヌルイコトヲシテイルカラダ、サッサトツカエヨ
その安堵は、
至天 「……僕は…」
コノガンコモノガ
簡単に崩れさる。
至天 「使いやしない!」
咆哮にも似たその言葉と共に、さらなる増大を果たす小宇宙、空気が爆ぜたようなその圧力の中で彼らは見た、
目の前の少年の体から鬼火の様な光が立ち上り、爪が、牙が、肉食獣のそれよりも鋭く伸び、
肌は夜の闇よりなお黒く、頭からは、先程まで確認出来なかった角が大きくせり出していた。

そしてその形相は、今までよりもさらに殺気と怒気を放出した、まさに鬼のそれに変わっていた
しかし、それ以上に目を引いた変化があった。
ゴトリと鬼の体に食い込んでいた銃弾が落ち、その体に刻まれた銃創が消える、
切り落とされた右腕を拾い上げ、無造作に切断面を合わせるとすぐさま元の通りに体の一部となっていた。
溥儀 「馬鹿な、あんな治癒能力が!」
その場にいた人間達が、驚愕に足を掴まれているその間に、二人の超人は反撃に転じていた。
シンエモン 「十歩氣功刃!」
レオンハルト「ベルリンの赤い雨!!」
流れ刃を避けるために長さを調節して繰り出された見えない刃が至天の首から足までの有った位置をそぎ落とすように薙ぐ。
巨漢の剛腕が手刀を形作り、唸りを上げて打ちこまれる。
シューターで有りながら、格闘能力を持つハイブリットタイプのレオンハルトの渾身の一撃、
しかも相手はシンエモンの攻撃を回避したばかりでかわせない、確信を持って放たれたその一撃は、
振り向き左腕を軽く頭の横に動かす、それだけの動作で受け止められていた。
レオンハルト「何!?ぬう!」
その事態に動揺する前に、ほとんど反射的に体を捻る、
踏み込みで大地を砕きながら目にも映らぬ速さで掃われた至天の右腕が、背に負っていた地獄の砲弾を打ち砕く
その衝撃で弾き飛ばされた巨体に目を向けず、溥儀に向き直ろうとした至天の胸に、鋭い熱痛が走る。
首を下に向け、自らの体を確認した彼の眼に映ったのは、自らの胸を貫く鏡の如く輝く一本の刃であった。
その刀身を片手で掴み、後ろの加害者を振り返る。
シンエモン 「悪いな、拙者も案山子では無いんだ」
そのまま万力の力を込め、一刀のもとに切り裂く、そのはずであった。
しかし、その両腕に握られた斬岩剣は、まるで一枚絵のように至天の胸に突き立てられたまま動く事は無かった。
シンエモン 『動…かん…!』
動きの止まったシンエモンが、斬岩剣ごと引きこまれる、後ろ向きに自分を掴もうと迫ってきた腕を、愛刀から手を離し、後ろに飛んで回避する。
井冨 「い、一体どういうことなのです?何故シンエモン殿の刀が?」
いつの間にか自分の隣に現れた井冨を訝しみながら、溥儀が口を開く。
溥儀 「恐らくだが単純な理由だ。
シンエモンが両腕で振りぬこうとする全身の力よりも尚、
あの男が片手で刀身を掴んだ力の方が強かった。というな」
井冨 「な、何を申されるのですか!シンエモン殿はS級…
超人の中の超人ですよ!?」
シンエモン 『成程、仮説通りこいつは鬼、という事か。
人ならざる存在、つまり超人である我々とは、
生物としての基本性能そのものが違う。
その膂力も、治癒能力も、そして・・・』
至天は、自らの肺を貫く刀に手を掛けると一気にそれを引き抜き、無造作に放り投げる。
ゴボリ、と肺に溜まった血の塊を吐き出し、口を拭った時には、今し方受けた致命傷クラスの一撃など初めから無かったかのように戦闘態勢を取る。
シンエモン 『生命力すらも』
至天 「退いてクダサイ、武器ヲ失っタあなタハ不利です。
ボクガ殺したいのはそのヒトダケです」
構えを解かぬまま静かに至天が告げる
シンエモン 「信じる者に降りかかる災厄と戦い、最後までその盾となって生きる。
拙者が剣を握った時に誓った事でござる。悪いが退く事は出来んな」
確かに、武器を失ったセイバーと、超人を超える怪物。
絶望的といっても良いであろう。
一瞬目を伏せた至天が低い体勢から両腕を広げ掴みかかる。何を思ったかシンエモンもそれを正面から迎え撃ち、そのまま組みつかれる。
相対しているのが、唯のセイバーで有ったなら
組みついたはずの至天の方が、焼けた鉄に接触したように反射的に飛び退く。
構えを解いた至天に、追撃の拳が突き立てられる、その腕から暁の輝きに勝るとも劣らない光が放出されている、
嵐の様な連打の中、樹木の枝葉をへし折りながら、大きく距離を取った至天だったが幾度となくたたき込まれた拳によるダメージと、
灼けた掌の皮膚が、全く再生を始めない事に戦慄していた。
【竜闘気(ドラゴニックオーラ)】
竜の騎士のみが持ち得る唯一無二のそれは、身に纏えばあらゆる攻撃を弾く最強の鎧となる。
そして一度攻撃に転じれば、その純度と出力、特異性によってか、それによって与えられたダメージの回復が極端に遅いという性質も持っていた。
武器を失えど、目の前の剣士には自分に有効な攻撃手段を持ち合わせている。
その事を念頭に置きながらも、背後から急襲を仕掛けたレオンハルトの腕を掴み、剣士の居る方向に投げつける。
もしこの時至天が、冷静な判断力を持っていたなら、
レオンハルトが急襲を仕掛けながらもシンエモンに集中している自分に感知できる程の気配を発していた事を疑問に思ったであろう。
しかし至天が巨漢の狙いに気付いたのは、投げ飛ばされた巨漢が投じた刀を、シンエモンがしっかと受け取った後であった。
その手に掴んだ愛刀に、自らの腕を覆っていた輝きが移る、逆手に構えたシンエモンが、雷光の如く速さで鬼と交錯した瞬間、
その輝きは一際大きくなり、僅かに身を捻り攻撃を流しながらも
胴を半ば両断された至天が地に倒れ伏した。
シンエモン 「シンエモンストラッシュ……B(ブレイク)」
チキ、と音を鳴らして太刀を構えなおし、
残心を取りながら自らの流した血だまりの中に沈んだ至天を振り返り、その小宇宙が消えそうなほどに縮んでいる事を確認する。
しかし、消えるまでは安心は出来んと、再び太刀に竜闘気を走らせ、にじり寄りながら気付いた、
その至天が血だまりの中で、ゼエゼエと荒い呼吸を繰り返しながら、僅かに顔を動かし、自らの主君を凝視している事を。
あそこに…居る、もう少しで……届きそうな場所に
……あの男の血族がすぐそこに………いる
今すぐに、殺せる場所に!
血を大量に含んだ土を砂塵の如く巻きあげながら。至天が走る、
気絶させられた者と溥儀を守るように円陣を組んでいた人垣を跳ね飛ばし、鋭く伸びたその爪が溥儀の心の蔵に食い込む直前彼は急停止していた。
でも僕は
その体を、巨漢の剛腕と剣士の愛刀に貫かれて。
本当に、この人を殺したいのか?
今度こそ、力無くズルズルと崩れる至天の姿を見て、言い知れぬ疑問が浮かび上がる。
レオンハルト「こいつの執念は一体何だ?
さっきの筆頭の一撃は致命のものだぞ」
それともう一つ、溥儀には疑問が有った、倒れる寸前、間近で見たこの鬼の目に浮かんでいたのは、
敵意ではなく迷いだった。一体……
その思考の最中彼らは気付いた、もう一つの薄気味悪い小宇宙に。
井冨 「良く解りませんが………まあ良いじゃ無いですか。お陰で」
近衛兵の一人が突如ガタガタと震えだす。心配して声をかけた同僚が声を失う、
仲間の腹から、突然奇怪な昆虫が肉を食い破って現れたのだ
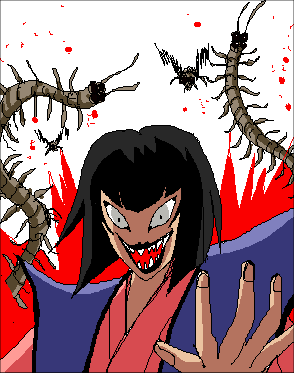
井冨 「ショーの準備も整いましたからね!!!」
シンエモン 「井冨!貴様グラップラーか!」
井冨 「そ、昆虫使い(インセクター)って言いましてね。
なかなか上手かったでしょ?僕一般人へのぎ・た・い」
言いながら、パチリと指を鳴らす。
それに呼応するかのごとく、木々が鳴動したように響いた羽音に目を向けると、陰から、顎が翅が肢が、
極端に鋭利に肥大化した異形の虫が飛び出すのが映る。大小様々な獣達の体を食い破って。
井冨 「どうです?僕のかわいい虫たちは、さあ、存分に戯れてくださいな」
近衛1 「な、何だこいつ等、ぐあああああああ!」
私兵1 「こ、こっちに来るんじ、ぎゃあああああああ!」
肥大化した翅を持つ虫に持ちあげられて宙に浮きながら発した井冨の叫びを合図に、虫たちが一斉に襲い掛かる。
ある者は虫が弾丸の如く体に突き刺さり、ある者はその鋭い顎に肉を抉られていた。しかし彼らは未だ幸運であったであろう。
異常事態に動転し、陣形からあぶれていた者たちは、抵抗をするしないに関わらず。その全身を異形の群れに覆い尽くされ、その命を食い潰されていった。
倒れた部下の前に立ち、迫る虫を愛刀で貫いた溥儀は空中を移動しつつ愉快そうに顔を歪める井冨を射通すような視線で睨みつける。
井冨 「おやおや、そんな怖い目で見ないで下さいよ。
僕だってあなたを殺せってクライアントの依頼でやらされてるんですから。
ああ胸が痛い胸が痛い」
溥儀 「貴様………、それならば何故昨日の内にやらなかった。
貴様の蟲を使えば暗殺も容易であろう」
井冨 「あれ?もしかして部下を巻き込まれて怒ってます?
そりゃあ筋違いって物だ、だってそうでしょう?
あなたが権力を持たず、能力を持たず、唯の人であったなら、
殺してくれなんて依頼が来るほど恨まれやしなかったし、
僕もせいぜい苦しめてやろうなんて思わなかった。
僕を逆恨みする前にご自分の罪を自覚しなさいな。
他人より高い位置に生まれてきたという罪をね!」
レオンハルト「筆頭!」
剛腕を持って虫を叩き潰しながら、その奇怪に歪んだ論説をかき消すように放たれたレオンハルトの叫びに、
同じく手近な虫を切り裂いていたシンエモンが一文字流奥義 烈風剣を放つ。
空中で慌てて大気の刃をかわし、態勢を崩し冷や汗を掻きながらも井冨は笑みを浮かべながら傲然と言い放った。
井冨 「危ないねえ。そういうの無しにしようよ、彼らに誓って?」
そう言って指を鳴らした音と共に、数発の銃声が響きシンエモン達に驚愕が走る。
それは突如放たれた狙いの甘いその銃撃による物では無く、それを放った四つの小さな影であった。
レオンハルト「マリー!?それに昨日の子達も、何故こんな所に!」
シンエモン 「待て、何か様子がおかしい」
自らの娘に駆けよろうとするレオンハルトを、シンエモンが片手で制す。
の言葉通り、そこにいる子供達は、一様に焦点の定まらぬ目をしており、歩調もかなり危なっかしい物であった。
そしてその首筋に、蜘蛛の様な腹が大きく膨らんだ体型に、大きな単眼を持った虫がへばり付いていた。
井冨 「気付いた様だね。その子たちはトルブスと言って、
脊髄近くまで差し込んだ針で人を操る可愛いやつさ。
下手に手を出したり、僕や仲間が殺されたりしたら
吃驚して針を刺しこんじゃうかもね?」
レオンハルト「シュツルム・ヴィント」
ケタケタと愉快そうに笑っていた表情が凍り、視界の中を埋める深紅の暴風を、自らの周囲を飛び回らせていた虫を盾にして対処する。
井冨 「なにするんだ!その子たちがど…うぇええ!?」
見せしめに一人刺し殺させようと、地上に目を向けると、
切られた事を知覚する事も出来ない速さで、微塵に刻まれたトルブスが落ちる。
すぐさま手近な兵士が駆けより、首筋に刺さった針を引き抜き、息が有る事を確認する。
さらに井冨を釣り上げていた虫が撃ち抜かれ、地上に叩き落とされる。
溥儀 「井冨よ、情報提供御苦労だったな。
俺の罪の前にお前の罪を裁くとしよう」
紫煙を燻らせる小銃を構えながらのその言葉に、井冨の顔が見る間に歪む。
トリブスに張り付かれた者を死なせずに助ける方法は唯一つ、
それは反応も警告を発する事も出来ない速度で針の有る頭部の神経節を破壊する事。
仲間がやられた事も知覚できない一刹那の間に複数体のそれを正確に破壊する。
不可能と思い口走ったその情報は、神技とも言える剣術の使い手たるシンエモンが居る場では、
言ってみれば、金庫の開け方を態々大声で宣伝したに等しかった。
シンエモン 「随分と幼稚な御高説を垂れていたが、他に言い残すことは有るか?」
無様に土を被った自分の前に、怒りを纏った帝国最強の男。絶望に彩られる井冨の顔が、
再び醜悪な悦びに染まった。
厳 「う、ぐぅえ、が、ああああああああああああああ」
その声に神経に直接冷水を浴びせられたような感覚を覚え、振り向いた先に見えた、
飛び散る鮮血と爆ぜ飛ぶ肉、
苦悶の声を上げその命を奪われた先程の子供達と、
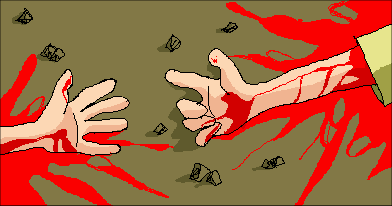
その体から抜け出て、手近な兵士に襲いかかる翅の生えた百足の様な虫。
悪い夢とすら思いたいその光景の中に、声を発するのももどかしいと言わんばかりに駆け出したレオンハルトを狙い、四匹の百足がその牙を向ける。
が、一拍遅れて飛来した目に見えぬ刃が、その内二匹の頭を切り落とす。
次いでレオンハルトの手に握られたショットガンが火を噴き、一匹を粉々に吹き飛ばす。
最後の一匹は大きく回避運動を取った所を、兵士数名の集中砲火を浴びる。
レオンハルト「マリー!!」
一も二も無く抱き上げた娘は、
先程まで脊髄近くに針を打たれて乗っ取られていた影響か、気を失ってはいるが、その体に外傷は無かった。
井冨 「おやおや、その子飲まなかったんですね。
折角の僕特製のフライングワームの卵入r」
ドチャアッ!
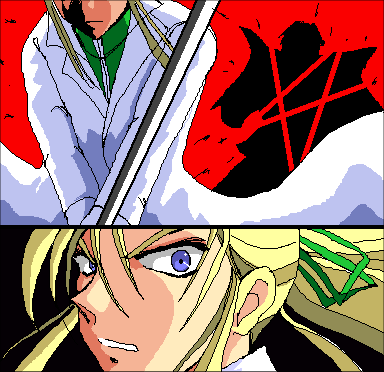
シンエモン 「喋るな。死ね」
言葉を発しきる前に、井冨の体が細かく刻まれ、音を立てて転がる。
それを成したシンエモンは怒りにその精神の大半を占拠されながらも、確かな違和感を感じていた。
その違和感を言葉にする前に、井冨と思っていた物が、ウゾウゾと蠢く大量の虫に変わる。
『擬態か!』
と思うその視界の端に、兵士達を跳ね飛ばしながら、小山の様な巨体を持つ甲虫が山の一部を削り飛ばしながら現れた。
ボタボタと土を振り落としながら、棍棒の様に変化した腕を振り上げる。
近くに居た兵士が放った戦車の装甲も貫く徹甲砲弾を意に介さず、発射の爆煙や衝撃で態勢の崩れた兵士を中足で薙ぎ払う、
そのまま前足が、片腕に娘を抱えて動きの鈍ったレオンハルトに狙いを定めた事を察し、間に合えと刀を持つ手に力を込めた時、
その巨大な甲虫の背中が熟れ過ぎた西瓜をたたき割った様に爆ぜ飛んだ。
ゆらりと立ち上がりながらも一撃を持ってそれを成した至天は、
そのまま片膝をつき、ボタボタと流れる血を撒き散らし荒い呼吸を繰り返しながら、
彼の肉に食い込んだ物を始め、彼を新たに攻撃目標とした虫達を握り潰し、叩き潰す。
相手の大きさは虫である。
如何に強靭な甲殻を持とうとも、その耐久力の限界は体の大きさ(甲殻の厚さ)に比例し決して高くはならない。
的も小さく個々では当たり辛いが、虚を突かれた状態から脱した事で連携を取り始めた兵にとっては
マシンガンで止めているうちにライフルの集中砲火を浴びせれば倒せない訳では無かったため、その数も限界を迎え攻撃が弱まりつつあった。
虫達の迎撃をレオンハルト達に任せ、井冨の気配を探り始めたシンエモンは目的の気配を程なくして探り当てる。
しかしその気配は、まるで何か薄い膜越しに有るような朧気な物であった。
疑問に思いながらも攻撃を仕掛けてきた虫を切り裂いたその時、叩き落とした虫の腹の中から、体液に混じった何かがシンエモンに付着する。
以前ウィザードクラスを相手取った時に感じた魔力にも似た物を感じた時、
それが放った光の中に、シンエモンの姿は消えていた。
先程交換した弾を殆ど使い切り、新しいマガジンを受け取ろうと動いていた溥儀は、その光景に驚愕する。
溥儀 「シンエモン!?」
近衛2 「上様、左から、うわ!」
近くの兵が虫に襲われながらもかけたその声に、僅かな自失から立ち直り、マガジンに残った弾を全て撃ち込み、虫を撃ち落とす。
その中から、シンエモンを光の中へと連れ込んだ、透明な結晶の様なものが転がり出る。
レオンハルト「上様!」
目の前を覆う虫を手刀で薙ぎ払いながら、溥儀の救出に向かおうとしたレオンハルトの足元にも、同じ物が転がり出た。
それが、僅かに輝きを発しているのを見てせめてもと、マリーを守るように抱えたレオンハルトの視界に、黒い塊が映る。
結晶の出す光の中心で虫の体液と自らの血に塗れた至天が結晶を弾き飛ばそうとしていた。
目も眩むような光が収まった後に突如投げ出されたシンエモンは、それでも周囲の状況を探りながら、綺麗な着地を決める。
木立に囲まれているのは先程までと同じだが、子供の見る悪夢に出てきそうな、おどろおどろしい暗く湿った空間、
何より先程までいた山中とは違い、周囲を何か悪意の様なものが取り巻いていた。
そのまま周囲を見回していたシンエモンの後ろから、二つの輝きが起こり、溥儀とマリーを抱いたレオンハルト、そして至天が地面に落ちる。
溥儀 「つつ、ぬ、シンエモン!無事であったか」
シンエモン 「上様、一体何故?お怪我は?」
溥儀に対し、その身を案じる言葉をかけつつ、溥儀を眺める鬼と溥儀との間に入る。
四人が顔を見合わせていると、パチパチと人を食ったような調子の拍手の音が響きわたる。
井冨 「ブラボー、ブラボー。ちょっと兵隊さんたちを甘く見過ぎていたよ」
溥儀 「井冨か、よもや貴様が隔離結界を所有していたとはな」
【隔離結界】
グラップラーという存在がこの世に出現してからという物、
その超常の力をどれだけ保有するかの絶対数が、国としての戦力の分かれ目と言って良い状況になっていった。
となれば当然、その差をいかに埋めるかの探求は永く続けられてきた。
隔離結界はその研究成果の一つであり、上手くすれば一方的なアドバンテージを稼げる固有結界の力を、手にするための物である。
これは、空間の保持に必要な大量の小宇宙を使用者の瞬発力に任せるのではなく、
少量ずつ時間をかけて備蓄しつつ、ウィザードの術式を解析した長大な魔法陣を刻みこんでおく事で、
クラスの低いグラップラーしか持たずとも、一時的な使い捨てとしての結界空間を展開する物である。
この結界空間は、固有結界の様に、「一方的に相手に不利な世界を作り出す」物では無いが、
晶石の様な「入り口」を使用する事で、対象物を誘い込み、状況的に有利な場所で迎撃出来る物である。
日本でも幾つか密造されていたが、完成目前に時の帝が率いる軍勢に攻撃を受け、その後何処かに廃棄されたとされる
井冨 「結構苦労したんですよ?僕の可愛い虫達に発掘させたり、
術式の文字を解読して僕好みのやつを探したり、
中に溜まっていた小宇宙をかき集めて足りない分は
更に僕の小宇宙を時間をかけて入れていったり」
何が仕掛けられているか解らない以上、この空間の中に居るのは溥儀達にとって不利にしか働かない。
破る為の最も解りやすい手段は、術者を倒す事であるが。
シンエモン 『気配が読み取れん……というよりも
この空間そのものが、奴の気配で満たされている。それにこれは』
レオンハルト『最初から此方が本命であったか…』
井冨 「さて問題です。僕はこの広大な空間の、どこに隠れているでしょう?
面の攻撃が苦手なセイバー君や
弾切れ間近のシューター君には難しいかな?」
何よりの問題は、あの大甲虫を含む先程までの数十倍、
否数百倍はあろう数の虫が、その羽音を字なりの如く鳴動させながら現れている事である。
その事態に、シンエモンと、レオンハルト、無用の長物と化した小銃から刀へと武器を持ちかえた溥儀が背中合わせに構える。
溥儀も異形の虫を(小型であれば)切り裂く程の剣腕は有しているし、レオンハルトも格闘戦でも得意の手刀で虫を叩き潰せる、
シンエモンは意功刃や烈風剣など離れた位置を薙ぎ払える技を持つ。しかしそれは全て、線の攻撃である。
兵の数によって死角を無くした状況ならばともかく、今の状態では何処かに隙ができるのは否めない。
それを理解しているのか、空間に響く声がゲームを楽しむような口調に変わる。
井冨 「さあレッツシンキングタイム。制限時間は、
あらゆる場所から襲ってくる虫の攻撃に君たちが餌になr」
至天 「ナゼ殺したンデス」
井冨 「あ?」
至天 「あのこドモタチを殺ス必要がアッタノカと聞いてイルンデス」
井冨の話の最中に放たれた、所々発音がおかしいその問い
調子よく喋っていたのを邪魔されたためか、不機嫌さが滲む声で答える。
井冨 「はあ?理由なんか決まってるだろ。
餓鬼って五月蠅いからだよ。いきなり何言っちゃってんの?」
馬鹿?とすら言いかねないその口調に、一瞬シンエモン達の怒りが頂点に湧き上がりかける。
今にも暴発せんとした怒りに冷や水を被せたのは、横合いに居た至天から発せられる冷たい怒りと、
至天 「何でこんな……僕は……こんな力なんか……」
シンエモン 「上様!レオンハルト!拙者から離れぬように!」
その内側に潜む何者かを本能的に感じたからである
井冨 「はっ!泣いてんじゃねえよ獣風情が!
バラバラに食いちぎられ続けても生きてられるか実験してやるよ!」
激昂したように井冨が叫ぶと同時に、空間を埋め尽くしていた虫達が、一斉に斑色の暴風と化して、至天を包み込むように襲い掛かる。
例え山を砕ける剛腕だろうが、素手の攻撃しかできない奴がこれだけの数に対応できるものか
その先に見えていたのは絶対的捕食者が被捕食者に対する様な勝利であったであろう
この時までは
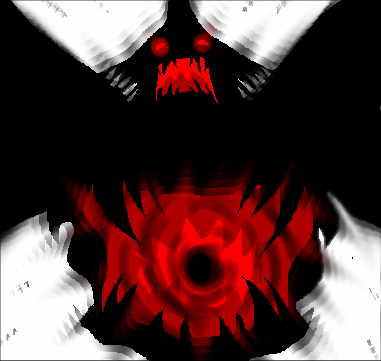
至天 「ツカイタクテツカイタクテ
タマンネエッテノニヨオ!」
鬼にも種類が有る。
純粋に身体能力のみが高い赤鬼、古からの呪法を知る青鬼等であるが、
その中で黒鬼はその肌の色ではなく、この言葉がなまって呼称が決まったと言われている。
「喰らう鬼」という言葉が
ぶらぶらと臓物を垂れ下げていた腹の傷がさらに開く、そこから大仰な牙と、毒々しい鮮やかなピンクの舌が現れ、ベロリとなめずる。
そのまま半分に裂かれたように上体がそっくりかえると、腹の口が大きく開き、無音の咆哮を発する。
その瞬間鬼のに喰らい付いていた虫が、気が変わったかのように突然地に落ち
その体がさらさらと細かい粒子に変わると鬼の腹に空いた口に吸い込まれていった。
井冨 「はえっ?な、何?何今の?」
震えるその声が響きわたると同時に、その眼に見えぬ何かは確実にその範囲を広げていった
それが此方へと向かってくる時には、シンエモンはすでに防御を始めていた
シンエモン 「竜闘気全開!ゆけえええええ!」
シンエモン達を飲み込もうとしたそれが竜闘気の壁で遮られる。
不可視のそれが確かに存在する事は、溥儀達の横、光の壁の恩恵を受けぬ虫や草や木が、分解されて鬼へと吸い込まれていく事で理解できた。
徐々に広がる命なき景色の中心で、鬼が牙を剥く。まるで、獲物を前にした肉食獣がそうするように。まるで、暗く黒い愉悦に満ちた笑みを浮かべるように
シンエモン達の後ろで、何かが転がるような音が鳴る。老病者の様な痩せ細った姿でその眼に見えぬ何かから逃げ延びた井冨であった。
冗談じゃない。折角準備をして、今から狩りを楽しもうとしていたんだ。何であんな予想外なのが出てくるんだ!?
何で僕が・・・命の危機なんてものに晒されなきゃならないんだ?
自分の周囲、僅かに光の壁に守られていた川の中州の様な一帯を除きすべてが、草一本無い荒涼たる死の大地に変わっている事を見て、
かろうじて僅かに残った虫達に攻撃命令を出しながら思考のループに嵌っていた井冨は気付かなかった。
首を掴まれて持ちあげられるその瞬間まで、目の前に現れた黒い鬼に
半ば恐慌状態に陥りながら、繰り出した拳が、蠅でも払うような軽い動作で砕かれる。
次いで自分を持ちあげている手が、僅かずつその力を増し、悲鳴にならない悲鳴が空気と共に漏れ出る。
突き出た牙も、せり出した角も、自らを掴む腕も今や全てが井冨にとって死が具現化した様にしか見えなかった。
パクパクと意味も無く口を動かす事しか出来ず。ただ理不尽なまでに絶対な死の予感だけを感じていた。
被捕食者が絶対的捕食者に対しそうであるように。
と、井冨の首を締めあげていた力が緩んだ
その期に乗じて、思い切り肺に空気を送り込みながら、まさか助かった?と淡い期待が頭を過る。
が、黒鬼の口角が思い切り吊り上げられると同時に、空いている片腕が無造作に腹の一片を掴み千切り取った。
ほんの少し自由を取り戻した喉は、再び込められ始めた力に悲鳴を発する事さえ出来ない。
振りほどこうと振り回していた脚が、丁寧に、執拗に、骨も肉もぐちゃぐちゃと混ざり合うまで砕かれる。
あげられない悲鳴の代わりとばかりに、滝の様な涙と鼻水と冷や汗が湧き出る。
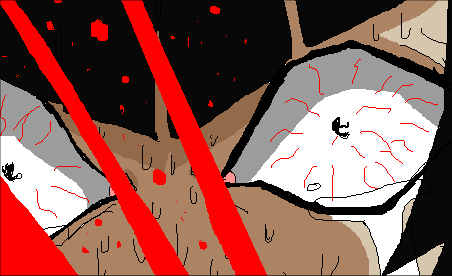
しかし手中の獲物のそんな様子など知った事かと言わんばかりに鬼は、殊更ゆっくりと獲物を解体していった。
もしこの鬼が拳の一つでも振るえば、井冨の体はぼろ屑の様に千切れて死ぬであろう。もし先程の技をもう一度発せばその体は一瞬で崩れ去るだろう。
それではだめだ。鬼の形相がそう語る
せっかくなら楽しまないと。そうして鬼は腕を振るう。痛みにのたうつ獲物を楽しみながら
殺虫剤を吸わされた虫の様に悶えていた井冨の動きが止まる、その命が無くなった事を確認すると、興味の無くなった玩具にそうするように投げ捨てた。
術者を失った隔離結界の境界が薄れいく中、その眼が溥儀達の方へと向けられる。
シンエモン 『ちょっと……不味いかもな……』
先程の大放出で竜闘気と体力をかなり消耗している。向こうは先程吸い取った命のおかげか腹の傷も塞がり、大甲虫を砕き飛ばすほどの力を持つ。
加えて先程の何かが又来るかもしれない、さらに努めて表に出さない様にしてはいるようだが傍らの巨漢の動きが僅かに不自然だ。
恐らくどこか痛めているのであろう、さてどうするか……と、思案を重ねるシンエモンの後ろから溥儀が進み出る。
溥儀 「…一つ質問が有る。貴様、二百年前の月形家の関係者か?」
その言葉に、一瞬眉を潜めた鬼はそのままにやりと表情を歪め、
至天 「アアソノトオリサ…アトイッポッテトコロデ、ケッキョクハタセナカッタ…
…ナ〜ンテヤドヌシサマハカンガエテルダロウガナア
オレハアンタノゴセンゾニハカンシャシテル、アイツラノオカゲデ、
コウヤッテダレカヲブチコロセルンダカラヨオ……コンナフウニナア」
再び無音の咆哮を放とうとした鬼にシンエモンが防御の用意をした時、その声は響いた。
??? 「間抜けが、撃たせなければどうという事は有るまい」
雷鳴の如く轟音と共に、鬼の左肩が弾かれ、紫煙を燻らせる銃口が現れる
それを中心に水の中に絵の具を垂らしたように広がり始めた純白の闇が、その領地を拡大させながら言葉を発する
ゆるゆると染み出していたそれが、明確な形を作る、紅いスーツに身を包み、ともすれば愛嬌すら感じられそうな、丸い大きな顔と三本毛の怪人
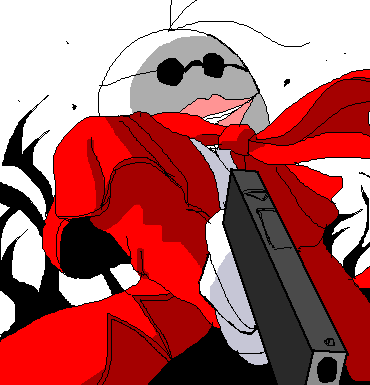
禁衛隊より古くから京都の闇を統べる異形の存在、魔人オーバーQ
その姿を認めた鬼の口角がぐいと突き上げられる。と、同時に跳ね上がった左腕を振りかざし、打ちかかる
至天 「ヒサシブリダナア、クサレマンジュウ
コマギレカラモドレルトハタイシタヤツダ」
オーバーQ「御覧の通り、怪我の治りは良い方なんでな
それよりどうする?私とシンエモン、二人同時に相手に出来るか?」
言いながら腹に蹴りを入れ距離を開く、と同時に右腕のバウ砲が再び火を噴く、先程の一撃を防御した折に千切れ飛んだ左腕を生やしながら。
腹に弾丸を喰らいながらも、なお好物を前にした獣のような笑みを崩さぬ鬼に、遥か彼方に過ぎ去った記憶が呼び覚まされる。
山を成す屍の中、自らの体から生え出した使い魔達を、自分の身長の五倍を超す金棒と大太刀を片手ずつで振りまわし薙ぎ払う鬼に相対した自分
血と硝煙と炎と死臭に塗れた甘美な記憶が。
オーバーQ「あんな溜めの要る物は隙を晒さなければそれで良い
シンエモンと私で接近戦だ、肋骨の折れてる肉達磨はお守でもしていろ」
溥儀 『情報を持つオーバーQの参戦は有り難いが…
それもこの結界が存在し日の光を遮る間のみ、やれるのか?』
溥儀の懸念を余所に、戦いは再び動き始めた
つ、と踏み込んだ鬼が片足を上げる動作にレオンハルトが足元への注意を促す。が、
その予想に反して、シンエモンの足元が崩れ去る事は無かった。レオンハルトとの戦いで見せた技は、先程の井冨の処刑に間に伝えてある
例え竜闘気で弾かれようと掠めただけで有効なほどの力が有る以上、地面を崩してでも動きを止めればその方が有利なのだから使ってくることも予想腕来た。
だから、シンエモンは自らの足場に予め僅かに気を送り込んでいたのである。地盤に干渉しようとした気を撹乱するために。
ユラと間合いに入り込んだシンエモンが、続いて放たれた暴風すら伴いそうな力任せの一撃をするりと、流麗とも言える体捌きでかわす
そのまま間合いを取ると手に持った太刀が、断続的に叩きつけられる。
水華流・大河の刃
静流の如く滑らかな足捌きを刻みつつ、怒る大河の流れが乗り移ったような激しい連撃を繰り出す性質の異なる体捌きと手捌きを両立させる水華流の高等技術である。
数十本の刀傷を刻みこみながら、内心で舌を打ちたい気分が湧きあがっていた。
シンエモン 『真の一撃は喰らわんか…』
連撃の単位時間当たりの手数が増えれば増えるほど、本当に力を込めた一撃の割合は少なくなる。
剣閃が視界を白く埋め尽くしそうな攻撃の最中、確かに鬼は皮を裂く仮初の一撃も並みのグラップラーならば両断されているであろう
肉を切る一撃もその身に受けながら、竜闘気を纏い骨を断ち命に届く真なる一撃のみをかわし続けていた。
連撃を終えた僅かな攻撃の隙間に再び雷鳴が四度轟く。
シンエモンが滑るように距離を取ると同時に、オーバーQが、弾奏に残った弾を撃ちこみ、距離を詰めていた。
『吸血鬼との近接戦闘は死を意味する』という言葉が有る
血を吸う知性を持った鬼である吸血鬼の剛力を指しての言葉であるが、もし相手が本物の鬼であればどうなるであろうか?
早くも刀傷の塞がりつつある鬼は、突きこまれた貫手を左腕を縦に突き出し手首辺りまでを貫かせて受けると、
残った右腕をオーバーQの右肩にかける、と、そのまま左の脇腹まで、古くなった壁紙を引き剥がすように一気に肉と骨を引きちぎる。
それを意に介さず残った左腕で顔を掴みにかかるが、掌ごと手首を噛みちぎられる。
先程の攻撃で落ちた右腕に握られていたバウ砲を体から生え出した犬の顎が掴み、再生した右腕が素早く装填作業を済ませ、
今度は千切られた左腕から生え出した犬の顎で噛み掴むと、六発全て右肩に撃ち込む。
と同時に溥儀と娘を背に庇い戦いの動静を見守っていたレオンハルトが、手に持ったショットガンの残弾を撃ち込む。
肩の骨ごと肉をこそげ落とされ、右腕が皮一枚でだらりと垂れ下がり腹にも銃弾を受け僅かに体制の崩された鬼に勝機を見、
再生のために反応の鈍る右腕側からオーバーQが、左腕側からは間合いで勝るシンエモンが肉薄していった。
背筋に一欠片の氷塊が滑り落ちたのはその時であった。
瞬きをする間もなく、鬼の攻撃間合いに入っていなかったはずの両名が弾き飛ばされる。
彼らは、或いは愛刀と竜闘気で、或いは使い魔と両腕で防御の体制をとりながら見た
自分達を弾き飛ばしたのが、鬼が自ら引きちぎった鬼自身の腕であったことを
振り回した腕の断面を叩きつけるように合わせ組織を再生させながら、腹の肉を突き破り再び大振りの牙と舌が現れる。
地面に打倒されながらも態勢を立て直し、攻撃を防ごうとするが、それよりも速くニイと口角を上げて再びあの口を開こうとした、その時
巨漢と将軍に抱え込まれて守られながら眠る、少女の姿が映る
その時、まるで別の生き物のように
宿主に反乱をおこしたように
左腕が開きかけた鬼の腹に突き刺さり、くの字に体が折り曲げられ、その口を閉じさせた。
鬼の顔から、戦いが始まってから、否恐らく此処に表われてから常に浮かべられていた笑みが消え、驚愕に変わる
その自失を鬼自身が自覚する前に、再び弾を込められたバウ砲がその咆哮を轟かせ、両の足へとその牙を突き立てる。
次いで現れた光の刃が、防御に突き出された両の腕とぶつかり、稲光にも似た輝きと共に根元まで吹き飛ばす、
その輝きが消える前に鬼の視界にたなびく金の髪の剣士が現れる、先程の光がかすむような輝きを放つ剣を振りかぶった剣士が。
シンエモン 「残りの竜闘気、全て持っていけ!
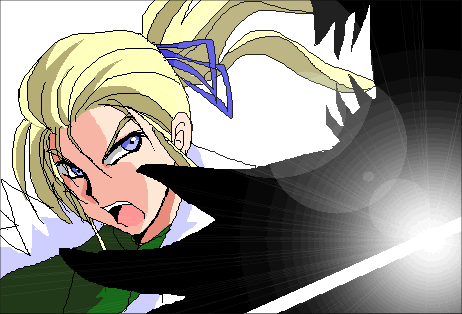
シンエモンストラッシュ・双・刃・断!」
全てを焼き尽くす太陽の様な光の奔流が、黒き鬼の体を引き裂いた。
ゼエゼエと肩で息をするシンエモンの目に、元の姿にもどる至天が映る
切り裂かれた肉の組織はピクリとも再生の兆しを見せずその小宇宙は急激に無くなり、目からは光が消えていく所が映し出された。
誰の目にもその命が消える事が見てとれたであろう。
辺りを包んでいた隔離結界の境界が、その形を維持する事が出来なくなり、ハラハラと崩れ落ちていく中
溥儀はゆっくりと末期を迎えようとする至天に歩み寄っていった。
至天 「……分かっては……いたんです」
溥儀がもう、二、三歩という位置に近づいた時に至天が口を開いた。
至天 「筋違いって……ことも……あなたが……
名君と…呼ばれるに値する……人物……で有る事も……」
途切れ途切れの弱弱しい言葉を、真剣な顔のまま聞き入る
至天 「けどね……理解…出来ても…
どうしても納得…できなか…た……僕は……」
つうと流れだした涙を見ない様に、溥儀が口を開く
溥儀 「君は、足利家を恨んでいるのだろう
しかしあの鬼を止めてくれたのも君だろう?」
一体何故?というその問いに薄い笑いを返す。
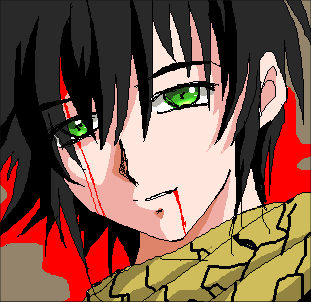
至天 「少しだけ……おわび………です…よ……」
そう言うと、僅かに瞳に残っていた光が消えていった。
もう一つの理由は、まあ良いか。カッコいい物でも無いし
地獄に行くと会えないだろうな……残念だな
境界が消え去り、彼らが元の場所に戻った時、鬼であった男の命は地に溶け、多慧山の戦いは一応の決着を見た。
溥儀 「やはり井冨の言っていたスポンサーは解らぬか」
シンエモン 「は、邸宅を隈なく捜させましたが何も
現在諜報部隊に裏を探らせておりますが、
それらしい繋がりは欠片も出てこずまだ何とも」
〜二日後〜
この二日間でそこそこ物事が動いた、負傷者への対応や、死者への弔いについての手配、多慧山内に残った虫がいないか、
いた場合山を焼くか一体ずつ駆除するかを決めるため又山中に廃棄されたアイテムが無いかの調査チームの編成、
夜間にも関わらずシンエモンの報告を聞いていた溥儀は、重苦しいため息を吐き出していた。
ちらりとシンエモンの方を見やると、目で何か有ったのかと問いかけていることを察し、口を開いた。
溥儀 「二百年前の造反事件の事を調べておった……」
この二日間仕事をしながら時折資料室に行っていたのはそういう事であったかと思いながらも、沈黙を守る。
そして聞いた、資料室の資料の僅かな改暫の後、反乱に与したとして打ち滅ぼされた豪族の横のつながりの系譜、
当時の物の動きとその時を知るオーバーQの証言、それらを総合して考えた時、
反乱を企てていたのは、足利家であった方が辻褄が合うという事を
シンエモン 「……しかし、確証は……」
溥儀 「無い…時間がたち過ぎているしな。だが調べるにつけ、
”月形家の企てた反乱を足利家が防いだ”よりも
足利家の企てた反乱の罪を着せられ月形家が攻め滅ぼされた
と考える方が収まりが良くなっていくのも事実だ
なあ、シンエモン。朕も自分に流れる血に
一点の汚れも無いとは思ってはおらん…
自分に課せられた責任が放り捨てて良いような類の物ではない
という事も理解している………だが、な……」
それきり沈黙に包まれたその場を、その丸い全貌を形作る前の月が照らしていた。
多慧山の一角、至天がその命を消した場所に、オーバーQは立っていた。ガサガサと包み紙の中から、一枚の板を取り出す。
月形家の屋敷跡地の地下から見つかった物である。絵画を特殊な晶石の中に保存し、時間の劣化から守る。
その技法で保存されていたそれをしげしげと眺めながら、手に持った瓶から琥珀色の液体を落とし、火を点ける。
パチパチと音を立てながら昇る青白い火に飲まれる絵画の中には、
穏やかそうな壮年の男性と長く滑らかな亜麻色の髪を持つ、美しさと愛らしさのその間にある少女、
そしてその背後につき従い、穏やかな笑みを浮かべる黒髪の少年が描かれていた。
ただ、そこにあった平穏を写しながら
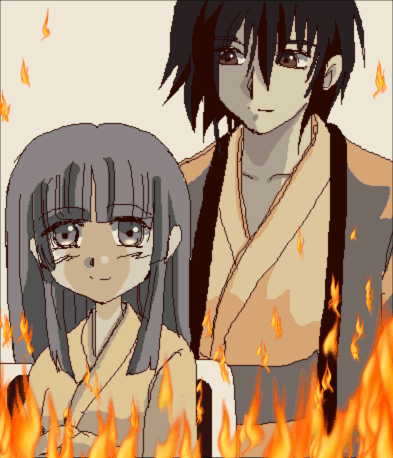
一体さん外伝
多慧山鬼譚〜昔々のケセナイキオク〜 終