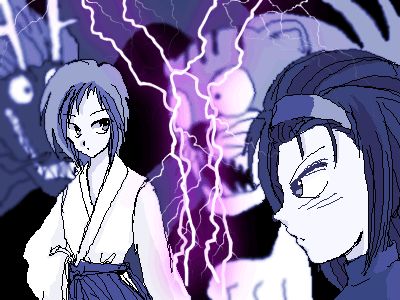
“一日彼氏”から明けて数日、木曜日の晩。
自室での読書という貴史のくつろぎは、突然鳴り出した携帯によって遮られた。
着メロは「スターウォーズ・帝国のテーマ」……景からだ。
「もしもし、貴史?こないだはほんとに助かったよ。感謝感謝♪」
「お前、もう少し友達は選べよな。まさかあんな恥ずかしいことまでやらされるとは思わなかったぞ?」
一つのジュースにストローを2本差して向かい合って飲むなんて、今どきマンガでもやらない。
「あはは、ノリのいい子たちだからね。」
「類友、か。」
「……何か言った?」
「いや、別に。ところで今日は何か用か?また妙な頼み事だって言うんならすぐ切るぞ?」
と言いつつ即切りした例しがないのはご愛敬。
「また、ってのはひどいなー。まるでいつもあたしが無理難題押しつけてるみたいじゃない。」
「違うとでも?」
「ま、まあその話は置いといて。次の土曜日、梅ばあちゃんが『今年も花見するよー!』って言ってるけど、貴史はどうするの?」
「行くよ。毎年の恒例行事だし。」
「そっかー。私は社務所の手伝いサボると夕ご飯抜きになっちゃうからなー。
あ、でも手伝いが終わり次第駆けつけるから、待っててね、ダーリン?」
「誰が『ダーリン』だ、誰が。」
「んもう、いけず。それじゃ、そーゆーことで。また土曜日ねー。」
土曜日、お花見の当日。心配されていた空模様も、見事なまでの快晴と相成った。
諏訪神社の境内に集まったのは、三人娘に貴史、小十朗や梅&美緒、ヘンリーとアル……ぶっちゃけ大三元の常連たちである。
ちなみにこの諏訪神社、桜の名所ではあるのだが、たどり着くためには殺人級の石段(通称「心臓破り」)を踏破しなければならないためそれほど混み合ってはいない。
いわゆる「穴場」のひとつだ。
「それでは始めるにあたって、番堂町内会長にひと言いただきたいと思います。」
よっこらしょ、と梅が立ち上がって挨拶する。
「えー、天気は良くて桜は満開で。これ以上の贅沢がどこにあろうかね。今日はみんなしっかり楽しんでおゆき。以上。」
「会長のあいさつも終わったところで全員飲み物は持ったな?それじゃ行くぞ?せーの……」
「「「かんぱーい!!」」」
「お、やってるね。俺っちも混ぜてもらおうかな?」
酒の匂いにつられたのか、現れたのは前掛け姿の立花元。
「元ちゃん?!屋台の方は大丈夫なのかい?」
この時期、大三元は花見客のために屋台を出している(無論、本店は臨時休業)のだが……
「ちょっとだけちょっとだけ。(プシッ!ごくごくごく)かーっ、うめえっ!」
と、旨そうにビールをあおる元の背中に突き刺さるのは槙絵の声。
「とーちゃんっ!ちょっとトイレ、とか言いながらやっぱりサボってた!!」
「ま、槙絵、とーちゃん、桜の魔力に操られてだな……」
「バカなこと言ってないで早く屋台に戻るよっ?!お客さん待ってるんだから!」
「痛ててっ!分かった、分かったから耳引っ張るなって!!」
「あ、みんな。後で差し入れ持ってくるから楽しみにしててね。」
元の耳を引っ張ったまま、槙絵は屋台へと戻っていった。
「槙絵ちゃんも苦労が絶えないねぇ……」
「ほんとにね……」
「さ、気を取り直して飲むとすっか。」
立花親子を見送ってた小十朗が、席の方へ目を戻す。
席の中央には、女性陣が持ち寄ったという色とりどりの料理が並んでいる。
「久々に腕をふるったからね。みんな、たんとお上がり。」
梅の勧めに、
「では、いただきます。」
几帳面にあいさつしてから、貴史はおいしそうに揚がっている唐揚げを口に入れる。
ゴリッ!
が、唐揚げをかじったとはとうてい思えない音が。
「つかぬ事を尋ねるけど、この唐揚げ、誰の持ち込み?」
「はいはーい、私わたしー。ゆうべお料理の本を見ながら作ってみましたー。」
と、恭子。
(いきなりジョーカー引いちまったか……)
口直しとばかりに卵焼きに箸を伸ばす。
しかし、卵焼きを口に入れたとたん、またもや動きが止まる。
「……この卵焼きは?」
「あ、それあたしです。一番きれいにできたのを持ってきたんですけど……どうですか?」
顔を赤らめつつ答えるのは摩弥。
「う、うん、なかなかだね……」
「兄さん、顔色が緑だけど。」
きっちり唐揚げと卵焼きを避けて料理を取りながら、一応兄を気遣う由宇。
「……挿絵でお見せできないのが残念です。」
* * *
うららかな日和のもと、宴は盛り上がっていく。
「いちばん、はすみきょうこうたいまーーす!」
「よっ、待ってました!」
と、その盛り上がりから少し距離をとっているような感じの摩弥に、由宇はつつつ……と近づいた。
「摩弥ちゃん、兄さんに何か話があるんじゃないの?」
「!」
「恋に悩む乙女のオーラが出てるのよね。」
ため息をつきながら、摩弥は答える。
「……由宇に隠し事はできないか。」
「(兄さんの方をチラチラ見てため息ついてたら丸わかりなんだけど)」
「貴史さんに聞きたいことはあるんだけど、何だか面と向かっては聞きづらくて……」
「そんな内気なあなたを、占い研のトップ占い師がお助けします。」
「トップも何も部員はあんただけじゃ…あいたっ!」
どこから取り出したのか、摩弥によく似た人形の首を90°捻る由宇。
連動して摩弥の首がありえない感じに曲がった。
「ツッコミは却下。それよりもこれ。占い研謹製スペシャルドリンク。」
由宇が差し出したものを見て、摩弥は首筋をさすりつつ懲りずにツッコむ。
「ただのコーラじゃない。」
「そう思うのがシロウトの浅はかさ。昨夜一晩ピラミッドパワーを蓄えたこの紙コップに注げば、ただのコーラだろうとスペシャルドリンクに早変わり。
聖なるパワーで気弱な人でも言いたいことをズバッと言える。」
「言いたいことを言える?……すっごくうさんくさい気もするけど、ものは試し、か。」
「ささ、ぐっと一息に。」
一気に飲み干す摩弥。
「……どう?」
「何だか体がかっかしてきて……うん、これなら何でも言えそう!」
「効果抜群ね。」
「ありがと、由宇。それじゃ行ってくる!」
「ぐっどらっく。」
ビシッと親指を立てて摩弥を見送る由宇。後ろ手に隠したオールドのミニボトルが気づかれなかったのは幸いである。
(※注 お酒は20歳になってから!)
皆のお腹も落ち着いて、ゆったりした雰囲気になり始めた頃……
「貴史さんっ!」
すごい勢いで摩弥は貴史に詰め寄った。
「どうしたの、摩弥ちゃん?」
普段なら真っ赤な顔でしどろもどろになるはずの摩弥の剣幕にちょっと驚きつつ貴史は応えるが、摩弥の口から出た言葉にはもっと驚かされた。
「この間の日曜日、お景さんとデートしてたでしょう?」
「!? な、何でそれを……」
「そんなことはどーだっていいんです!デート、してたんでしょう?!」
「ちょ、ちょっと待って。あれはデートとかそういうんじゃなくて……」
「向かい合ってジュースまで飲んで、デートじゃなきゃ何だって言うんですか!」
「(そんなとこまで見られてたのか)だからあれは諏訪に頼まれてやっただけなんだってば。」
「ほほぉ〜、『頼まれて仕方なく』な割には貴史も嬉しそーにやってたように見えたけど?」
こめかみに青筋を立てて貴史の背後から現れた「お景さん」。
手伝いが終わって着替えもせずにやって来たのか、巫女服のまんまである。
「す、諏訪……」
「あたしとジュース飲むのがそんなにイヤだったわけ?貴史は。」
「誰もイヤとまでは言ってないだろ!そりゃかなり恥ずかしかったけど。」
「イヤじゃなかったんなら、貴史さんの意志であんな恋人同士みたいなことを?」
「俺の意志ってわけじゃなくて、その、あの場はああするしかなかったわけで……」
「それじゃ頼まれたらあーゆーことでも素直にやっちゃうんですか?!」
この場はどちらに付いても後が怖い。ただひたすら嵐が過ぎるのを堪え忍ぶしか無い、と悟る貴史であった。
「百歩譲ってこないだのデートはOKとしても、お景さんとだけじゃ不公平!あたしだって貴史さんとデートしたいです!!」
「だめー!それは絶対だめー!!」
摩弥の爆弾発言に、景が猛反対。
「何でダメなんですか?貴史さんはお景さんの彼氏なんですか?!」
「か、彼氏とかはっきりそこまでは……その……」
「彼氏じゃないんだったら、貴史さんが誰と何しようが自由でしょ?
貴史さんはお景さんの所有物じゃないんだから、行動を束縛するのはおかしいです!」
「う、それはそうだけど……」
「さて、どう読む?」
丁度いい余興だとばかりに、小十朗がのんきに尋ねる。
「そうですな、◎本命がミス諏訪、○対抗がミス葛城というところでしょうが、この場はミス葛城に勢いがあるように見受けられます。」
これまたまったく動じる様子もなく、冷静に分析するアル。
「ほほう、なかなか鋭いね。」
「恐れ入ります。」
そうこうしている間にも、バトルはますますエスカレート。
「とにかく!あたしと貴史はねー、中学校以来のベストパートナーなの!」
「一緒にいた時間の長さだけで決めるっていうの、ズルいと思います!」
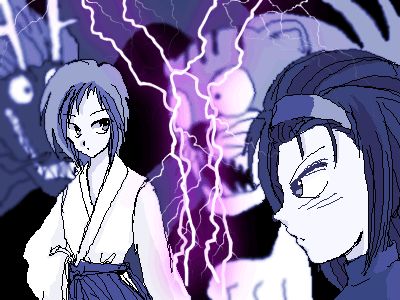
二人の間にはチリチリと稲妻が走り、バックに「龍虎相討つの図」がドドーンと浮かび上がる。
「あ、あの、二人とももう少し落ち着い……」
何とかなだめようとおそるおそる声をかける貴史であったが……
「「貴史(さん)は黙ってて(ください)!!」」
「はい……」
二人に一喝され、すごすごと引き下がる。
「両手に花って言うか。もてる男はつらいねぇ、貴史にーちゃん?」
にやにやしながら、美緒は貴史の脇腹を肘でこづく。
「美緒ちゃん、どこでそんな言葉覚えてくるんだよ。そんなのんきな状況でもないよ?これは。」
一触即発、いつ決戦の火ぶたが切られてもおかしくない、と皆がハラハラしている中に割って入ったのは梅の声であった。
「二人ともその辺にしときな。貴坊が困ってるじゃないか。
何より花見の席で痴話げんかってのは無粋だろ。酒は楽しく飲むもんさね。」
盃を傾けながらの一見おだやかな口調であったが、目が笑っていなかった。
(逆らったらヤバい、てゆーか殺される)
老いたりとは言え如月組の親分さんも一目置くほどの女傑、小娘二人が太刀打ちできる相手じゃない。
二人は渋々ながらも臨戦態勢を解除、周りから安堵のため息がもれる。
以降は、少なくとも表面上は何事もなく時が過ぎていった。貴史を挟んで座った摩弥と景の間に、密かに火花が散っていたとしても。
「貴坊、ちょっとおいで。」
片付けも終わり、各自解散という時に、貴史は梅に呼び止められた。
連れてこられたのは少し奥にある、一番年季の入った桜の下。
「実際のところ、どっちが好きなんだい?かたや中・高6年来の相方、かたや一途に自分だけを見てくれる。二人ともいい子だよ。」
「どっち、って言われても……なぁ。」
「歯切れが悪いねぇ。それとも何かい、もうしばらくぬるま湯のままでいたい、っていうクチかい?」
「ちょ、ぬるま湯だなんて、いくら梅ばーちゃんでも言っていいことと悪いことが……」
「悪かったよ。今のは年寄りの戯言ってことで聞き流してくれりゃいい。だがね、貴坊。
あんたは昔から優し過ぎるくらい優しい子だったから『誰も傷つけたくはない』って思ってるかも知れないけど、結局は一人しか選べないんだよ?」
「それは……そうだけど。」
「特に色恋沙汰はすべて八方丸く収まるなんてこたぁ無いんだから、白黒はっきりさせてやるのもまた優しさってもんさね。」
「…………」
「ま、何も今すぐ決めろってんじゃない。じっくり考えて答えを出せばいいさ。
ただ、ずるずる引き延ばしても誰も幸せにゃなんないってのを肝に銘じておきな。」
ひらひらと手を振って、梅は境内を後にした。
その後ろ姿を見送りながら、貴史はぽつりとつぶやいた。
「白黒はっきり、か…………
それが簡単にできればこんなにも悩まないんだけどな。」
<了>