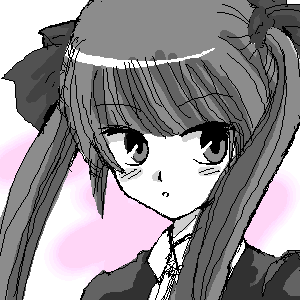
「ふぅっ、なーんかつまんないよなー」
校舎の屋上で、赤毛の少女・サキはけだるそうにつぶやいた。
おもむろにポケットから煙草を取り出し、手慣れた所作で火を付ける。
シポッ!
紫煙をくゆらせる姿もなかなか堂に入ったものである。
スゥーッ……
「げほっ、げほっっ!」
……前言撤回。
「こらっ、女の子が煙草なんか吸っちゃダメでしょ?」
くわえ煙草でぼんやりしていたサキの後ろから声が聞こえた。
振り向くと、声の主は上級生と思しき柔らかな雰囲気の女生徒。
腰に手を当てて、ぷんすか怒っている。
「……んだよ。アンタにゃかんけーねーだろ。」
思いっきり悪態を付くサキにちょっとびっくりしたようだが、女生徒はかまわず続ける。
「そりゃ関係ないかも知れないけど、未成年なんだから煙草吸っちゃダメなんだし、ましてや女の子なんだから体を大事にしないと……」
一生懸命に説得する彼女を見ているうちに、何だかものすごーく悪いことをしているような気になり、サキは煙草をもみ消した。
「ちっ、煙草がマズくなってきちまった。分かった、消すよ、消しゃーいーんだろ?」
「あは、分かってくれたんだ♪」
まるで自分のことのように喜ぶ彼女に、興味を覚えたサキ。
『周りの奴らなんて、みんなアタシのことをまるで腫れ物の様に避けてるってのに。』
「……なあ、あンた、名前は?」
「わたし?九條恵美っていうの。」
「メグミ……か。覚えておいてやんよ。」
「あの、あなたは?」
何故だか素直に答えてしまう。
「……サキ。眞柴サキ。」
「サキ、ちゃんか……とってもいい名前ね。」
「ばっ?!な、何言ってやがる!!」
「ふふっ、いいじゃない♪」
「あーもーっ、チョーシ狂ってしょーがねー!」
足早に昇降口へ向かうサキの背中に、恵美の声が届く。
「もう煙草吸っちゃダメだからねー。」
……不思議とイヤな気はしなかった。
この日から、屋上で会うたびサキと恵美は少しずつ言葉を交わすようになっていった。
初めは「物好きなヤツもいるもんだ」程度に思っていたサキも、いつしか屋上に出ると恵美の姿を探すようになり、
姿が見えないと少しがっかりしてしまう自分に気が付いた。
そして今日も、昼食後のひとときを他愛のない雑談で過ごす二人の少女の姿が屋上にあった。
サキ、大☆変☆身!
リョウ・アマバネ
「なあ、恵美……さンは将来の夢とかあるのかな?」
さわやかな初夏の風に吹かれながら、ふとサキが口を開いた。
「そうねぇ、今のところ特には無いし……強いて挙げれば“お嫁さん”かな。」
「ったく、3年生がそんなんでいーのかよ。」
「うっ、痛いところを突かれちゃった。で、そう言うサキちゃんは?」
「ア、アタシ?!そ、その、言っても笑わないか?」
「もちろん。」
「アタシ、トリマーになりたいんだ。」
「トリマーって、ペットの美容師さん?」
「ああ、それそれ。」
「サキちゃん、動物好きだからピッタリよね。」
「ヘヘ、でも単に『好き』なだけじゃ務まらないみたいだけどな。相手にナメられちゃダメだから、時にはビシッとシメなきゃなんないらしいし。」
「ふぅ〜ん……サキちゃんは自分の将来のこと、ちゃんと考えてるんだ。えらいなー。」
「別にそんな大層なことでもねーよ。でもさ、恵美さンだって成績いいんだろ?だからアタシ、てっきり進学するもんだとばかり思ってたけど。」
「お父さんは大学に行ってもいいって言ってくれてるんだけど、家の手伝いが好きだし、あんまり負担かけたくないから。」
「家の手伝いって、恵美さンちって商売か何かやってんの?」
「あれ、言ってなかったっけ。うち、雀荘だよ?」
「じゃ、雀荘?!」
「変……かな?」
「い、いや、変とかそーゆーんじゃなくって、恵美さンちは何となくお堅い職業かなーってイメージがあってさ……。」
「……それじゃ、うちに来てみる?」
「え?」
「ほら、サキちゃんこの前のテストで英語が赤点すれすれだったって言ってたじゃない。
次のテストはもうちょっと先だけど、うかうかしてられないからね。サキちゃんさえよければわたしが英語を見てあげるけど?」
「え?ホントか?!」
「はい、決まり。それじゃさっそく今日の放課後からね。」
後輩の勉強を見る、ということで雀荘の手伝いを免除してもらい、恵美はサキを自分の部屋へと案内した。
恵美の人となりを反映してか、清楚で落ち着いた印象を受ける部屋である。
「何もない部屋だけど、くつろいでてね。いまコーヒー入れてくるから。」
サキを残して、恵美は一階へ下りていった。
キョロキョロと部屋の中を見回すサキ。
「ふぁ〜〜……」
「お待たせー……サキちゃん?どしたの?」
2人分のカップとコーヒーサーバー、砂糖やミルクを乗せたお盆を手にした恵美が問いかけると、サキは我に返ったように答えた。
「あ、うん、何か『大人〜』な雰囲気だったんで見とれちゃってさ。」
「ふふっ、ありがと。」
恵美はまずサキのカップに、続いて自分のカップにコーヒーを注いだ。ふくよかな香りが部屋中にたちのぼる。
「はい、どうぞ。お父さんには及ばないけど、味にはちょっと自信ありなんだ。」
「えーと、それじゃ……いただきます。」
「サキちゃん、お砂糖いくつにする?」
「みっ……ふたつ。」
「くすっ、サキちゃん、甘党なんだ。」
「な、何だよ、悪いかよ。」
「ううん、何かかわいいなぁって。」
「ちぇっ。言ってろ。」
淡々と英語の勉強は進んでいく。恵美の教え方がいいのか、サキもだんだんと詰まることが少なくなっていった。
そして一時間ほど過ぎた頃であろうか。
目の前の英文に集中していたサキがふと視線を上げると、恵美が自分のことをじっと見つめていることに気が付いた。
「じぃ〜〜〜〜っ」
「どしたんだよ、人のことじろじろ見て。アタシの顔に何かついてんのか?」
「……サキちゃん、地がいいんだからもっとおしゃれしたらいいのに。」
「アハハッ、おしゃれなんかガラじゃねーよ。どーせ似合わねーし。」
「そんなことないよ。よし、決めた!」
「へ?」
「わたしがサキちゃんをコーディネートしてあげる♪」
「ちょっ?恵美さン?!目が怖ぇよ?」
「ふふふ〜、お姉さんにまっかせなさ〜い!」
「うぁああああ!お助け〜〜〜〜!!」
:
:
:
「はい、出来上がり〜。」
「……すっげえ恥ずいよ。」
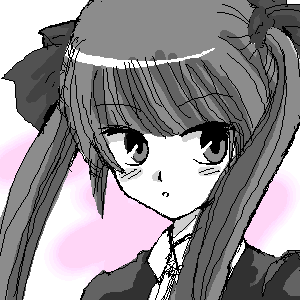
鏡の中には、フリフリのワンピースに身を包み、髪をツインテールにまとめた女の子。
「自分でやっておいて何だけど、ここまでかわいくなっちゃうと妬けてきちゃうわね。」
「なあ、恵美さン、もういいだろ?」
「だ〜め、帰るまではこの格好でいること。」
「う〜〜〜〜……」
ヒジョーに居心地が悪いながらもサキが勉強を続けていると、
「あ、コーヒーなくなっちゃった。おかわり淹れてくるね。」
言うが早いか恵美はカップとサーバーをお盆に乗せ、部屋を後にした。
「…………」
恵美の足音が小さくなるのを確かめてから、おずおずと鏡の中の自分を見つめるサキ。
「ホントにアタシ……だよな。」
黒地に白いフリルのワンピース。髪をまとめた赤いリボンがよく映える。
最初は座ったまま見ていたのが、立って見るようになり、ポーズを取ってみたり、くるっと回ってみたり。
興が乗ってきたようである。
「てへへ、こんなのも悪くないかもな。そ〜れ……って?!!」
もう一回ターンを決める途中、半回転したところで、
にこにこしながら自分を見つめる恵美とバッチリ目があった。
階下でコーヒーを淹れているはずではなかったのか。
「うんうん、口ではいやだって言ってても、やっぱり気に入ってくれてたんだ♪」
「〜〜〜〜〜!!」
頭の中が真っ白になり、サキは口をぱくぱくさせることしかできなかった。
「こっそり見てたけど、かわいかったわよ?サキちゃんのファッションショー。今度は別の服でやって欲しいな。」
へなへなとへたり込んで呆けるサキにお構いなく、クローゼットから次々に服を引っ張り出す恵美。
「まずはこれかな。牌楽天の制服。あ、こっちの方がいいかも。でもでも、これも捨てがたいなぁ……」
眞柴サキの明日はどっちだ。
<了>