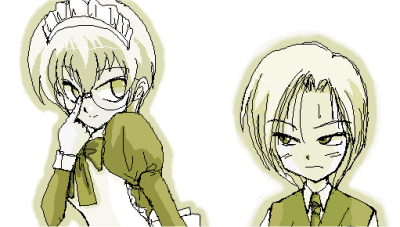
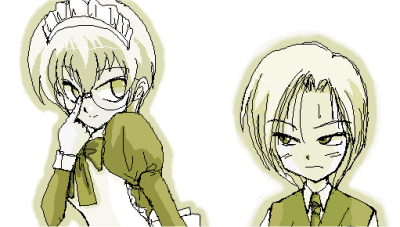
犯罪は家人の楽しみ 〜クレイトン家の人々〜
おむすび(鮭)
現在クレイトン家の一室では、小さな事件と大きな事件、二つが起こっている。
一つは、ヘンリーのチェス三連敗。こちらは小さな事件。
もう一つの大きな事件は、今もなおパソコン画面上に残っているチャットのメッセージにあった。
エラリー・クイーン:「優しきチャンプに神のご加護がありますよう」 (2003/07/02
16:53:02)
この後、すぐに彼女(もしくは彼の可能性も)は対戦部屋から退室している。
なぜこれが大事(オオゴト)なのかと言うと、
エラリー・クイーンは、対戦相手がヘンリーであることを知っていたという事実『も』メッセージに含まれているからである。
ヘンリーが使用したインターネットによるチェスは『チェストネット』という世界最大のチェス運営サイトである。
サイトの名前であるチェストネットは、トップ画面には大きな宝箱(チェスト)があり、
それをクリックすると、CGで描かれたチェスの駒が、コミカルに踊るというところに由来する。
「チェス」と「チェスト」という非常にベタな掛け合わせだが、利用者の大半はそのことには気づかないし、気にすらもとめない。
むしろチェストネットではなく、チェスネットと覚えているユーザーの方がはるかに多い。
ネット対戦という特質上、相手の顔、名前や年齢、もちろん性別すらわかるべくもない。
チェストネットは、数百万人(サイト側公表)が愛用しているポピュラーなチェスの対戦ゲームであり、
北はアラスカから、南はなんと南極までと、サイト自体が英語を使用していることを除けば、
文字通り、世界中のチェス愛好家達の憩いの場となっている。
HN(ハンドルネーム)の入力さえすれば、誰でもチェスを指せるという気軽さも、ユーザーを惹き付ける要員のひとつである。
ネット対戦自体は、かなりシンプルな造りであり、申し訳程度の簡単な会話をこなせるチャット機能を除けば、
対戦相手との交流の手段は画面の盤上、つまりチェスの対戦でのみとなる。
現役最年少チェス世界チャンピオン、ヘンリー=ウィリアム=クレイトン少年の、HN(ハンドルネーム)は「バイロン」。
そして三日連続三連敗を喫したチェスプレイヤーの名前(HN)は「エラリー・クイーン」であった。
前者のバイロンは、18世紀に活躍したシェークスピア以来の天才詩人であり、
後者のエラリー・クイーンは、20世紀中頃に一世を風靡した米国ミステリー文学の第一人者である。
その日、ヘンリーがバイロンというHNを選んだのには、深い理由はなかった。
前日にバイロンの詩集に目を通す機会があった、それだけのことである。
一度だけ、実名でチェストネットで対戦相手を探し求めたが、モニターの向こうの対戦相手は誰も信じなかった。
彼が思っている以上に、ヘンリー=ウィリアム=クレイトンの名前は、チェス界では大きかったのである。
完膚なきまでに相手の駒を蹴散らして証明しようとしても、
その全員が「本物の天才少年はもっと強いぞ」と、稚拙な負け惜しみから個性的な言い回しまで、
多種多様ではあったが、異口同音に口を揃えた。(むろんチャットでだが)
それ以来、気の向いた時にその日の気分をHNネームにつけては、気軽にチェスを楽しんだ。
日によっては、有名なサッカー選手であったり、戯曲作家であったり、
季節を感じさせる我が家の庭園に生える木々や美しい花の名であったり。
余談ではあるが、クレイトン家の庭園は、世界でもその美しさで知られる「コットンガーデン」と比肩するほど、それは見事なものである。
ただし、一般人への開放は行えないため、美しい芝と木々の調和の妙を知る人はごく限られる。
地上に顕現したヴァルハラと見紛う庭園が、関係者以外に未公開な理由は、ただ一つ。
幸せを貴族階級だけで独り占めしよう......という利己的なものではない。
純粋に国家保安上の重大な問題である。
クレイトン家は代々大英帝国を公の立場では政治の中枢を支える屋台骨として存在してきた。
しかし、ユニオンジャック(英国国旗)を火にくべようと画策する悪漢が、仮にそれを実行しようとした場合、
真っ先に標的にしなくてはいけないのは、偉大なる女王陛下ではなく、クレイトン家なのである。
クレイトン家さえ混乱に陥れれば、英国は元より、国交のある国、企業、そして宗教までもその影響を受けざるをえない。
そのため、クレイトン家とその家族にはあらゆる保安処置がなされている。
当然、屋敷内はもとより、東京ドーム何十個分と換算するのも馬鹿らしくなる広大な敷地内にも、
あらゆるセキュリティシステムとSPが存在している。
毎月、SAS(英国特殊部隊)の訓練と、クレイトン家のセキュリティ保全の両方を兼ね、
隊員の内、狙撃手が定期的に庭園内に潜入し、家人の狙撃を試みるが、これまで一度たりとも成功に至っていない。
もちろん実弾ではなく、ペイント弾であり、クレイトン家としては、狙撃対策とセキュリティ網の穴を見つけるため、
SAS側としては、世界でも類をみない潜入の難所での実地訓練となっている。
また、それらのデータを元に、より安全な庭園の造形を加えていくわけだが、
庭園の外見を全く損なうことなく、絶妙に配置させているあたりが風土と歴史に裏打ちされた英国気質であろう。
そして目に見える防衛網以外に、現代では欠かすことのできない世界最高の防衛網がもう一つ。
家人の私用電話から国家機密ファイルの送信まで、あらゆる通信及び電子的攻撃を排除する防壁、
『アイギス』というコンピューターセキュリティシステムによって、クレイトン家は完璧に守られている。
これらを管理維持しているのはMI6(英国情報部)の電子諜報部を筆頭に世界から集められたその筋のエキスパートである。
世界でも難攻不落と謳われるセキュリティはいくつか存在している。
アメリカ合衆国国防総省のコンピューターセキュリティシステムは、通称「ペンドラゴン」。
無断で立ち入る者を全て焼き尽くすという意味と、国防総省のペンタゴンを文字った攻撃的なシステム。
ノーラッド/北米航空宇宙防衛軍司令部のセキュリティはその通称「シャイアンホール」という。
巨大な落とし穴を彷彿させるセキュリティ形状(電子的比喩)であり、トラップにかかったハッカーは文字通り奈落へ案内される。
最終戦争を想定し、シャイアン山をくりぬいて核ミサイルを詰め込んだ世界最大の"バカの穴"として有名である。
そして表向きは英国情報部の、通称「イージスシールド」。
ギリシャ神話の登場する無敵の盾であり、いかなる攻撃にも耐えうる絶対防御のコンピューターセキュリティ。
アテネの盾を突破しても、その後に鏡面のようにゼウスの盾が控えており、二枚を同時に破壊しなければこのシステムは破れない。
盾の内側にいる利用者の特定は、あらゆる方面において実質不可能となる。
この3箇所のコンピューターセキュリティシステムは、世界の暗躍するハッカー達の最終目標となっている。
つまり、ヘンリーが大衆娯楽のチェストネットでチェスを指そうが、日本のサイトを覗いて回ろうが、株価を操作しようが、
彼がアイギスシステムに守られている限り、人物の特定をするなど不可能なのである。
ところが、エラリー・クイーンなる人物(仮名)が、バイロンをヘンリーと特定した。
当然アイギスシステムは彼(もしくは彼女)の前にが立ちふさったわけであり、
世界チャンピオンを破るチェスの天才(仮定)は世界最高のハッカーである可能性が浮上したのである。
たかがチェスの話で、なぜここまで危険視しなければならないか。
アイギスシステムをハッキングできるということは、クレイトン家を電子的に攻撃できることと同義だからなのである。
クレイトン家をほんの少し揺さぶれば、世界中に少なからず余波が及ぶ。
もしそれが、重要な局面で起こりえたとした場合、100回に99回は大丈夫だとしても、それはセキュリティとしては意味を為さない。
ヘンリー少年がチェスに敗れたことは些事であるが、
そこから生じた状況証拠は、少なくともクレイトン家の一大事に発展しそうなのである。
これらを踏まえていただいた上で、話を少し戻してみよう。
〜 ヘンリーが一敗目を喫する午後 〜
「きゃっ!」
「うわぁっ!」
開けた扉の向こうにいきなり人が立っていたりすると、普通の人間であれば、多少なりとも心拍があがる。
ヘンリー少年は普通とは程遠い才能の持ち主ではあるが、この場合に活かせる能力があるかと問われれば、皆無である。
それがごくごく親しい者であったり、美しい女性であったとしても、心の準備というものは必要である。
そして、人間は行動を瞬時にとめられるようにはできていない。
車ではなくとも、人間だって急には止まれないのである。
あえて先に弁護するが、ヘンリーの身長はこれから伸びるという点で彼には非はない。
扉の先にいた人物と衝突した際に、非常に柔らかくほどよい弾力の感じられる部分に、
その幼い顔を埋める格好になってしまったとしても、彼にはなんの非もなかったのである。
世間で言うところの、そう、事故である。
幸か不幸かは、当人の立場やら感覚やら感触やら感情やらその他もろもろが複雑に絡み合うため、この際不問としよう。
「ドっドっドっドドアの前に黙って立ってるなんて悪趣味だよ。クレア!」
耳まで真っ赤になりながら、盛大に後ずさるヘンリー。
「ノックをしようと思いましたら、いきなりドアが開いたものですから.....。」
抜けるような白い肌、その頬をほのかに染めながら、口元を手に持っていた紙で隠す女性と一言でいうには若く、
美少女と形容するには、醸し出す雰囲気はやや大人びている。
短くすっきりと切りそろえられた白金色の髪と、知的なノンフレームの眼鏡、レンズの奥には淡い碧眼。
古くからデザインの変わっていない、クレイトン家のメイド服を一部の隙もなく身に付け、
よく観察しなければわからない、白いブラウスの襟の部分に、銀の狐が刺繍されている。
銀狐(シルバーフォックス)はクレイトン家の紋章である。
敷地内に三桁は軽くいる使用人達のなかの、ごくごく限られた者が銀狐を身に付けることを許されている。
服への刺繍であったり、装飾品に掘り込んだりと、その形は本人の自由であり、彼らは総じてオフィサーと呼ばれる。
その基準は経験、技能、実績、家柄等、多岐にわたるが、
クレイトン家を支える重要な人物、あらゆる面で信頼に値する証として与えられる、といったところであろうか。
クレイトン家嫡男であるヘンリー付きのメイドであるクレアは屋敷内最年少のオフィサーである。
『で、何か用事が.....』
『どちらにおいでに...』
お互い照れのようなものを隠すために、視線をそらしながら口にでた質問の声が重なる。
なにやら気まずい空気を感じつつ、ヘンリーは年齢にふさわしくはない咳払いを一つすると、もう一度質問を投げかける。
「撲に何か用事が.......って、手紙を持ってきてくれたんだね。」
ヘンリーはクレアの手元を見て、質問の答えを自分で出した。
たしかにクレアの手には、手紙とおぼしき封筒の束がある。
「はい。急ぎのものでは無さそうです。」
クレアはほんの少し、主にはわからない程度の意味深な微笑みを浮かべながら、ヘンリーに10通の封筒を渡す。
どの封筒もサザビーズオークションの競売でも出てきそうな、しっかりとした古風な造りで封蝋(紋章付き)のおまけ付き。
それぞれの封筒の裏に書かれた差出人達の名前と、封を切る前から漂ってくる香水の匂いに、盛大にため息をつく。
全てが由緒正しく誉れも高き貴族女性、しかも全員が年上であり、内容は読まずともわかる。
初夏のお茶会のお誘い、初夏の乗馬のお誘い、初夏の避暑地へのお誘い、初夏のダンスレッスンのお誘い、初夏のお勉強会のお誘い...
まだ社交界にデビューしてないヘンリーにとっては、いずれも建前上、お勉強会以外は無縁の世界なのだが、
上流階級であってもインプリンティングと恋の駆け引きは同列くらいに有効な手段である、と信じられている。
まだ子供とはいえ、一夏を共に過ごした男女というリードはかなり大きいというのが、彼女達の一致した意見である。
家系図を遡れば、親戚の知り合いの友達のご近所くらいの血のつながりがあるであろう淑女のお姉さま方は、
あの手この手で、ことあるごとに可愛いヘンリー君に気の早いアプローチをかけてくる。
色恋沙汰にはまだ興味がわかない健全な少年にとって、
これらの手紙の返事を書くのは、夏の風物詩と割り切るにはいささか食傷気味のイベントである。
断りの手紙だから適当に書いてもいいだろうと思い、上流階級は非常に狭い世界であることを痛感したのは2年前。
『今年の夏は海外の○○に行く予定を立てているので残念ながらうんぬんかんぬん.....』
といった内容の返事をしたため、海外のどこに行くかは、それこそ地球儀をクルリと回してエイヤっと指にとまった場所。
ヘンリーはその年の夏、南米の密林に、モンゴルの砂漠に、アフリカのサバンナに、太平洋のど真ん中に、大西洋に地中海にと、
それぞれに出した手紙の返事の内容を合わせたら、世界各国同時出没という偉業を為したことになってしまった。
まさか、手紙の差出人達が『ヘンリー君のお返事』を持ち寄って整合性を確かめるとは........
そして、ヘンリー君のついた可愛いウソが、さらに彼の人気を急上昇させたという乙女心は、天才少年の理解の範疇の外である。
「........あれ?去年は苦労した記憶がないな......」
手紙の束をアゴにあてながら、再び記憶の道を戻ろうとした矢先、
「昨年はチェスの世界選手権で、ご多忙でらっしゃいましたから。」
クレアは、まるでヘンリーと同じ回想を一緒にたどっていたかのように、さらりと解答を示す。
「そーか......そうそうそうだったねぇ。」
「今年は昨年の一般参加の予選からではなく、ディフェンディングチャンピオンとしてシード枠からの参戦となります。」
「すっかり油断してたなぁ.....急いで頭を切り替えなくっちゃね。」
ヘンリーは憂鬱な作業からの脱出口を見つけ、少年らしい笑顔を浮かべる。
滅多に見られない少年らしい表情に、少なからぬ幸せを感じつつ、
クレアは主人の疑問と要件、当面の目標が決まったところで、彼女自身が当初しようとした質問を問いかける。
「それはそうと、どこかにお出かけの予定ではなかったのですか?」
「ん?あぁ、僕はこの本を書庫に返しにいこうとしてただけなんだ。」
ヘンリーは手紙の束とは別の手に持っていた厚いカバーの本をクレアに見せる。
「バイロンの詩集ですね。」
「読むだけは読んだけど、僕にはちょっと早かったみたいだね。
どちらかというと彼の波乱万丈な伝記の方にするべきだったかもね。」
「では、その本は私が書庫に戻しておきます。
伝記の方は後ほどお持ちいたしましょうか?」
「あ、いや、自分で........」
「使用人は主人に命じられてこそ本懐でございます。と、言いたいところですが、
私も借りっぱなしになっている本を返さないといけないので、ホントのところはついでなんです。
ヘンリー様は書庫へ本を返却しに行くほんのちょっと浮いた時間を有意義に使ってくださいまし。
初夏のお嬢様方にお返事をしたためるもよし。
世界選手権に向けてチェスをお励みになるもよしでございます。」
手紙の返事と聞いて、ヘンリーはがっくりとうなだれる。
「わかった。有意義な時間の使い方を検討することにするよ。
伝記の方はまたの機会にするから、詩集を返しておくのだけお願いするね。」
書庫は、日当たりの良いヘンリーの部屋から、屋敷内をグルリと回り込んで裏手になるため、それなりの距離になる。
クレイトン家の書庫は屋敷の裏手、ちょうど日陰になる三階建ての別棟が丸々蔵書の保管場所となっている。
書庫とは通称の立派な図書館であり、歴史的に貴重な文献も多く、大学等からの貸し出し依頼などに対応する司書も数名いる。
また、クレイトン家の関わるものであれば、使用人であっても禁帯本以外の貸し出しも奨励している。
こうした図書の閲覧などは、充実した環境の一端にすぎず、
クレイトン家に仕える者はその他、様々な知識や経験を自然と身に付けていく。
短い期間であっても、クレイトン家で仕事をしていたという履歴がつけば、一流企業でも引く手数多となる。
「さてと......有意義な時間か。」
クレアが去った自室で、ヘンリーはパソコンの電源を入れると、チェストネットへと回線をつないだ。
もちろんこの時、これから起こる不思議な出来事と、懐かしい出会いを含める、ちょっとした事件を知るべくも無い。
〜 ヘンリーが三敗目を喫した午後 〜
ヘンリーがあの日より三連敗を喫した相手。
ハンドルネーム『エラリー・クイーン』はともかく、彼が誰であるか、ヘンリーには確信があった。
大胆な駒の犠牲、運び、意思、忘れることの出来ない盤上の展開。
既視感などではなく、一度対戦したことのある相手であるとい確信。
しかし、現実という壁がその確信を突き崩す。
彼(彼女?)が彼であるはずはないのだ。
なぜなら、マクマソンは亡くなっているのだから