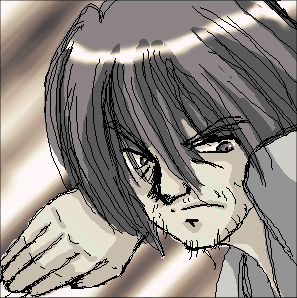
からくり麻雀物語外伝
小十朗伝
『代打ち〜出会い〜』
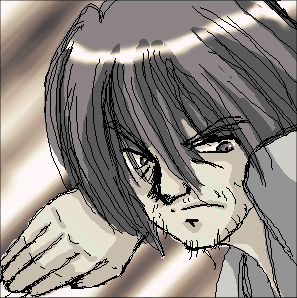
おむすび(鮭
無力な老人のように思われた。
少年にとっては楽な獲物のはずだったし、後は対象を掴んで引き抜けばいいだけだった。
陽の沈みかけた薄暗い公園、背もたれ付きのベンチで居眠りをする老人。
やや年季を感じさせるチャンチャンコに身を包み、
一昔前の画家よろしく頭に乗せているベレー帽は、一定周期でコクリコクリと首の動きに合わせて舟をこいでいた。
その隣に、まるで孫のように寄り添って座る少年。
ラフな服装に身を包み、目深に被った帽子とスタジアムジャンパーは、汚れや毛羽立ちが目立った。
一見どこにでもある風景において、唯一違和感を指摘するならば、少年の手の動きであった。
まるで支えるかのように老人の胸元に手を添えている。
正確に記すならば、その手を懐に忍ばせていた。
少年の表情に戸惑いや怯えはなく、むしろ周囲に対してすら無警戒なまでに首から上を動かしたりはしない。
犯罪において通常という言葉は適切ではないが、スリは複数の人間で行うのが常である。
周囲の警戒をする見張り役、財布を抜き取る実行犯、場合によっては抜き取った後の財布を受け取る渡り役がいる場合もある。
それが観光地の浮かれた獲物であっても、終電の酔いつぶれた獲物であっても同じである。
少年のそれは出来心からつい盗みを働くといった仕草ではなかった。
これまで何度もその技、その犯罪に手を染めた常習犯としての動き。
その眼光は素早くあたりの動きを確認し、絶妙のタイミングで老人の財布を抜き取る....はずだった。
「....っ!?」
悲鳴や驚きの声を上げなかったのは、いっそ見上げた度胸であったと言えよう。
スリの少年が財布の代わりに掴んだ、いや掴まされたのは、真っ白な鳩であった。
なんせ鳩である。
生きているのである。
クルックーとか鳴くあの鳥類なのである。
数年後に有名な某映画監督がことあるごとに使う平和の象徴なのである。
少年の脳内がまともでもそうでもなくでも、こういった状況を分類するならば理解不能という言葉が適当だろう。
そして、不測の事態に陥った場合の最良の策とは、一刻も早くこの場を離れることである。
使い古されたスニーカーで脱兎のごとく逃げ去ろうとしたその瞬間、ありえないことが起きた。
少年の左足と、アスファルトにがっちりと固定されているベンチの足が手錠で繋がれていたのである。
「ふぇっふぇっふぇっふぇ」
一瞬のことに走り出そうと勢いをつけてしまった姿勢を戻すことも出来ず、地ベタに不様な形でひれ伏すこととなった少年。
怪しくも愉快そうに笑うその声は、つい数秒前まで獲物であった老人の髭に隠れた口元からもれていた。
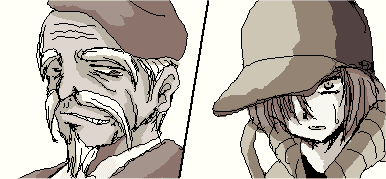
「無力で哀れなジジイの財布をかすめとろうとは、血も涙もない子供よなぁ。白鳥園の小十朗君や。」
少年はこの『仕事』をする時、自分を証明する一切のものを身につけなかった。
学生証は当然、服には全て名前が入っていないし、
仕事を行う場所も、電車で数駅離れた都心を選んでいた。
それにも関わらず、この無力で哀れを自認する老人は少年の名前と住んでいる場所....
少年が産まれてから、その大半を過ごしている孤児院の名前を出したのである。
どこまで知られているのか?いや、それよりも、まず逃げなければならない。
もし少年の仕事が世間にバレれば、そしてこの『仕事』を続けられなくなれば、彼の帰る場所はこの世のから消滅する。
それだけは絶対に避けなければならない。
冷たいアスファルトに顔を押し付けたまま、絶対に使うまいと決めていた腰のナイフへと手を伸ばした。
自分のことを知られてるからには、脅すだけではダメだ。
この老人の背後に誰がいようが、現状から脱出しなければどうにもできない。
覚悟を決めてナイフを握ろうとして、彼は三度、愕然とした。
「そんなところに這いつくばっとらんで、ほれ、隣に座るんじゃ。
リンゴでも剥きながら、小十朗君とのビジネスの話なんぞしようかの。」
老人の手には、血のように赤いリンゴ、そして小十朗のナイフが握られていた。
足にかけられた手錠といい、自分のナイフといい、いつ、どのようにかけられ、盗られたのかがわからない。
小十朗は、未知の体験に対する恐怖という感情を、この老人が警察の人間ではないという確信で押さえ込んだ。
「あんたが誰かは知らないが、見逃してくれるんだったら何でもするさ。」
80年初頭、世間ではリーゼントに長ランという型に嵌りきった不良とくくられる人種が溢れる世の中において、
中学生の岩倉小十朗は、表面上はごく普通の少年だった。
彼は親の顔を知らず、その人生を物心ついた頃から孤児院で過ごしていた。
町内会や零細企業からの支援で成り立っている小さな孤児院『白鳥園』は、贅沢とは縁遠い場所であったが、
血の繋がらない8人の子供たちが、毎日を賑やかに過ごしていた。
そして何より、年老いてはいるが信頼できる園長とその娘の存在が、陽光のような若芽である少年少女達に暖かい光をあてていた。
そんな小さな幸せを摘み取ったのは時代の流れであったのか、はたまた人の悪意であったのか。
善意で借り受けていた白鳥園の建つ土地が、二束三文の価値から、まるで石油が湧き出る場所のような値段に跳ね上がった。
後に地価狂乱と呼ばれるバブル時代の象徴である。
左に善意、右に大金を天秤にかけた時、聖人でもない限りは大きく右に傾く。
それまで無償で貸し出されていた白鳥園の土地は、いきなり月額数十万円の賃貸物件となった。
それが払えなければ立ち退いてもらい、取り壊された建物の後にはマンションなりビルが建つこととなる。
身寄りの無い子供達が、その後どうなろうが知ったことではない。
この理不尽な仕打ちに対し、園長を先頭に、周辺の土地を離れたくない住民は一丸となって立ち上がろうとした。
が、その運動も園長が「何者かによるトラックの轢き逃げ」に遭うまでの短い期間でしかなかった。
未だに意識不明の園長に変わって、その娘と子供達の中では最年長の小十朗が支えようにも、
数年間続けてきた唯一の収入源である新聞配達のバイトは、なぜかいきなりクビにされた。
役所への相談は子供だけでは端から相手にもされず、
それどころか、孤児院で暮らす8人の子供たちをどこへ移動されるかを検討し始める始末だった。
日々の地上げ屋と呼ばれるヤクザの嫌がらせと、迫りくる家賃の期日、そして弟妹たちを食べさせるため、
小十朗は陽の当たる場所から暗がりへ、その場所を守るために抜け出せない暗闇へと進んでいったのである。
半年間に渡り、小十朗はスリという犯罪行為を糧として、自分の居場所を、自分の大切な仲間を守っていた。
「毎月毎月、匿名での資金提供。
これまで地上げ屋に流れた金から察するに、小十朗君が稼いだ金額は軽く7桁じゃな。
ここまでの補導歴なし。見事な腕前と胆力ではあるのぉ。
しかし........先週からマッポに目をつけられてることまでは知らんじゃろ?
もっとも風体だけで、リストに名前まで載ったわけじゃないがの。」
老人は小十朗がおとなしく隣に座ると、次々と自分が握っている情報という手札を見せてきた。
彼の現在の状況を正確に把握し、なおかつ警察の動きまで知ることのできる立場であること。
「警察にマークされてる俺を使って何をさせたいってんだ?」
スリとしての腕を見込んで、老人の言うビジネスをさせるのであれば、警察の警戒対象となっているらしい自分を使うメリットは薄い。
かといって、この老人がいわゆる同性愛者であり、そういう関係を強要するとは到底思えない。出来れば思いたくない。
どちらにしろ、前者なら犯罪の片棒を担いでその上前を、後者なら後々強請りの材料にすればいい。
彼に今必要なのは、相手の情報と、それをどう換金するかである。
「そうさのぉ、マッポに捕まるのは小十朗君も何かと困るじゃろうしのぉ。
毎晩このジジイの相手をしてもらおうかの。
1晩につき3万もあれば当座はしのげるじゃろ?」
覚悟は決めていた。
しかし、いやらしく笑う老人を見て、さすがに悪寒と鳥肌を押さえることはできなかった。
「はたしてこの老人を満足させることができるかのぉ。
見たところ経験があるようには見えんが..............」
口角の左右を引き上げながら、老人はナイフの切っ先をで小十朗の指先に近づけながら、
「当面はここと、ここ」
ナイフが触れるか触れないかのギリギリを楽しむように、そして刃で舐めあげるに腕からこめかみへと進めた。
「ここと、最後にここの鍛錬じゃな」
こめかみから眼球にピタリと突きつけられたナイフは、
その瞬間、魔法のように消え失せると同時にドスっと小十朗の心臓へと突き立てられた。
死に直結するその行為は、鋭い刃ではなくナイフの柄の部分によるものだった。
「明日のこの時間までにこの本の内容を頭に入れてくるのじゃ。
きちんと覚えてこられれば次の仕事をやろう。
もしできなければ、そうさのう.....客をとらせるのも悪くないかの」
下卑た笑いと共に、いつの間にか皮を剥き終わっているリンゴと一緒に本を手渡された。
本のタイトルは『類人猿でもできる麻雀』。
おそらくどこの書店でも簡単に手に入るような、ごくありふれた麻雀というゲームの入門書である。
パラパラとめくると、最後のページには1万円札が三枚挟まっていた。
「最後まで儂についてこれればそんな小銭どころではなくなる。
そうなれば小十朗君の孤児院の方も潰されずになんとかなるじゃろうな。
まぁ、その根性と胆力があるかどうかは先の楽しみじゃがの」
どっこらしょとかけ声をかけながら、一人ベンチを離れようとする老人に、小十朗は慌てた。
「おい、ちょっ!爺さん!手錠手錠!」
話を聞いている間も、小十朗の左足は手錠でベンチとつながれたままである。
明日のこの時間までこの状態にされるのはさすがにまずい。
すると、老人は振り返り、例の下卑た笑いを浮かべながら、
自分の目のあたりをトントンと叩くと何事もなかったかのように去ってしまった。
その背筋の伸びたうしろ姿は、先ほどまでの腰を曲げたヨボヨボの老人のそれではなかった。
「......目?目を鍛える?」
自分の右足を見ると、先ほどまでの頑丈な手錠は消え失せ、代わりに手品やびっくり箱に使われる万国旗が巻き付いていた。
この後、岩倉小十朗は奇妙な老人と三ヶ月に渡り、文字通り毎晩を共に過ごすこととなる。
麻雀における基礎と理念、人間の心理と操り方、賭け事における鉄則、そしてその裏と表の全ての技術を小十朗は叩き込まれた。
老人の名は片岡重蔵。
裏の麻雀界ではその名を知らぬ者はいない伝説の重鎮であり、広域暴力団出雲組の代打ち『筆頭』であった。
敗北は一つの終焉
敗北こそが全ての始まり
いま無敗伝説の幕があがる
次回小十朗伝『代打ち〜東局〜』乞うご期待