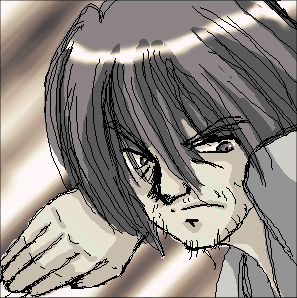
小十朗伝
『代打ち〜東局〜』
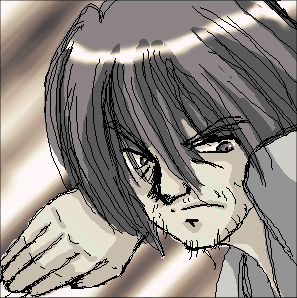
おむすび(鮭
好きなように打つ。
それが小十朗に課せられた、最後の条件だった。
出雲組は日本有数の広域暴力団である。
平たく言えば、全国規模に組織を展開しているヤクザである。
直系となる12の組から派生する関連組織の数は、数百とも数千とも囁かれる。
出雲組系雀王戦。
数年に一度行われる一大イベントは表裏を問わず、
麻雀という賭博に魅せられ、その腕を活かそうと思えばこの機会を外すことはできない。
参加人数32名、3回戦のトーナメント方式で優勝賞金が一千万円。
さらに優勝者には、その後に特別卓での結果如何により、
日本でも有数の広域暴力団『出雲組』の代打ちとなれる機会が与えられるのである。
都内の一流ホテルの一室に設置された会場には、手積み用と全自動の麻雀卓が1台ずつ。
それぞれの手牌が見える角度から、TVカメラが設置されている。
その様子は巨大なパーティ会場にて放送され、全国から集まった出雲組系の関係者、及び上客が観戦するところとなる。
もちろん観客にとっては、このイベント自体が賭けの対象となっている。
もし出雲の代打ちとなれば、一晩で動く金は最低でも億単位。
その重責を物ともせず、組に貢献した時に代打ちが得る報酬は、雀荘で素人から毟る小銭の比ではない。
よって、麻雀の学生チャンピオンから、誌上プロと呼ばれる表世界のプロはもとより、
全国津々浦々の裏プロ達もこぞってこの雀王戦出場を目指す。
無様な麻雀を打つようなレベルは参加申し込みすらできるはずもなく、
参加資格は、一定の戦績を証明できること、
出雲組系列の人間で、これまで何らかの貢献があること、
出雲系代打ちの推薦者であること等様々ではあるが、
要約すると、子供がチョロチョロと出てきて許される場所ではないということである。
賭けの対象となる出場者のプロフィールの中で、
少年の年齢が14歳であること、麻雀歴が3ヶ月であることを見た者は、まず失笑する。
それから推薦者欄に、現出雲組系代打ち筆頭の名前を見て、様々な興味と憶測を巡らせる。
最後に岩倉小十朗の負けをもって、片岡重蔵の負けと見なす、という一文がさらに混乱を呼ぶ。
希代の代打ちの自信か策略か....はたまたイベントにおける余興か、さもなくば.....いよいよボケたか。
人寄せパンダであろうが、人喰いコアラであろうが、出場者も観客も、全ての人間が小十朗という少年に注目せざるを得ない。
一人の堅気もいないこの空間で、興味本位と蔑み、中傷と奇異の目を向けられた中学生の快進撃が始まる。
片倉重蔵との出会いから三ヶ月間、小十朗の生活は肩までどころか頭の先までどっぷりと麻雀に浸かり続けるものだった。
思い通りに賽の目を出し、自在に牌を積み込み、自由に牌を抜き取る。
有利不利を問わず、あらゆる状況での打ち方を学び、最終的に場の支配する。
文字通り血のにじむような努力はあったものの、
重蔵の教えたことを、一度で理解し実践できたのは天性の才能と環境の賜物であったろうか。
最初の1ヶ月が過ぎる頃になると、マンツーマンだった指導から実戦へと移り変わった。
ごく普通の雀荘からマンション麻雀、さらに地方の卓と様々に引っ張りまわされた。
大人びているとはいえ、さすがに麻雀という賭事の場で子供だけが打つのは難しく、
大抵の場合は、一局のみ重蔵が打つ。
その後、お決まりの持病だの発作やらで、孫役の小十朗が代わりに打つという流れができあがっていた。
麻雀を打つ際の条件は、その日その日によって重蔵から出され、それをクリアしないと報酬は出ない。
例えば、
対戦相手の3人を同時に飛ばす。
東3局までに自分の持ち点を1000点まで減らした後、南4局の親番で逆転。
対面に3回連続で役満をあがらせる。
対戦相手のローズ(通し)を把握した上で、相手にばれていることをそれとなく悟らせる。
積み込みを阻止する。
全ての上がりを3900点にする。
自分以外の3人をオーラスで同じ持ち点にする。
等々。
小十朗にとっての麻雀とは、対戦相手に勝つことではなく、
重蔵の出す条件をクリアすることによって、報酬が得られるという手段でしかなかった。
その結果として、小十朗は一度も報酬を取り逃がしたことはなかった。
条件を達成する方法は、これまで重蔵に教えこまれた知識と技の中にあったし、
面倒な時は、自分の中で勝手に技や手法を組替えたり、作り直したりもした。
楽しむことを含んだゲームとしての麻雀ではなく、あくまで稼ぐ手段として。
それが小十朗という少年が覚えた麻雀の全てだった。
タキシードなどという着慣れない正装に身を包み、
豪勢ででかい外車(後にロールスロイスということを小十朗は知る)に乗せられ、
一流ホテルのロビーを抜けてパーティ会場へ。
この三ヶ月で様々な世界を見せ付けられてきた小十朗ではあったが、
今回ばかりは別世界であった。
そんな小十朗にとって、「好きなように打て」という条件は、鎖から獣が解き放たれたというよりは、
可愛らしいかどうかともかく、室内犬がいきなり外に出されたようなものである。
いつも傍らにいた、師匠、もしくはクソ爺と呼ぶべき片岡重蔵はここにはいない。
受付に必要らしい書類に小十朗自身に名前を書かせ、それを受け取ると、
重蔵はいつものフェッフェッフェという笑いと共にパーティ会場の中へと消えていった。
そして現在、重蔵と入れ違いでやってきて小十朗の側を離れないのは、
身の丈が2mを越えるマウンテンゴリラである。
と言ったら、ゴリラの方が機嫌を損ねるかもしれない、要約すると肉厚な大男である。
顔つきは、出来損ないのフランケンシュタインがさらに整形に失敗したような感じであり、
気の弱い人間なら、近づかれただけで卒倒してもおかしくないであろう、出雲組の構成員の一人らしい。
案内役兼、付き人として、小十朗の行く場所に向かう場所にことごとくついて回っている。
呼吸音がウッホウッホと聞こえるような気がするが、多分人間に分類されるんだろうなとは思う。
立食形式のパーティ会場では、豪華な料理がずらりと並び、
会場の正面に設置された巨大なモニターでは、別室で行われている一戦目の闘牌が中継されている。
各選手の表情、手牌、そしてオッズが表示されており、
一局終わるごとに、会場ではざわめきが起きている。
そんな異様な空気に包まれた空間で、大男を引き連れた少年はモニターとは別の意味で注目を浴びている。
「でさ、いつになったら俺の順番?」
「..........。」
「俺麻雀打ちにきたはずなんだけどさ、爺さんどこ?」
「..........。」
「これ、喰っていいんだよね?」
「..........。」
「あんた喰わないの?バナナあるぜ、バナナ。」
「..........。」
「後でタッパー借りれっかなぁ。ウチのチビ共にも持って帰りたいんだけど。」
「..........。」
「一人で喰っててもあんま旨くないよなぁ.....」
言葉とは裏腹に、とりあえず手当たり次第、自分の手の届く範囲の料理を片っ端から口の中に押し込めつつ、
お付きの大男とコミュニケーションをはかろうとして、小十朗はそのことごとくに失敗していた。
もしかしたら日本語が通じないのかもしれないと思い始めた頃に、
後ろからぶっ太い指でドスンドスン(間違ってもトントンではなかったように思われる)と肩を叩かれた。
振り向くと、大男はアゴでついてくるようにという動作をしている。
モニターでは既に先ほどの対戦が終わっており、どうやら次は自分の出番らしい。
麻雀卓が準備された部屋では、既に3人の男が席についており、
立ち会い人とおぼしき黒背広の人物が一人、そこにまるで影があるようにひっそりと立っていた。
雰囲気に呑まれたりする小十朗ではないが、
卓についている3人より、その立会人にはどこかしら薄ら寒いものを感じた。
「これより出雲組系雀王戦第二試合を行います。」
小十朗が卓につくとすぐさま立会人によるルール説明が始まった。
備え付けのカメラは全て無人のオートらしく、先ほどの会場にこちらの表情が放送されているだろう。
簡単に言えば、東風戦のトップのみ勝ち抜けである。
上がりは頭ハネとなる、ごく一般的な東風ルール。
賽は二度振りであるが、手積みの段階で裏技、俗にイカサマと呼ばれる技術は公認であると言ってもよい。
最初の山が既に組まれている以上、大きな仕掛けをするには次局の親が誰になるかが重要となる。
今回小十朗に課せられている条件は「好きなように打つ」である。
拡大解釈をすれば、好きなように打てば勝とうが負けようが、関係はないということになる。
しかし、起家となってしまった上に、子供と思って油断、もしくは中傷の視線を送ってくる対戦相手に、
わざわざ勝ちを譲ってやれるほどの義理も人情も彼にはない。
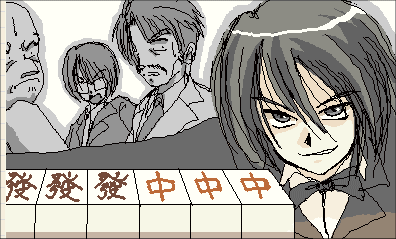
巨大なモニターの向こうで、オッズ20倍の少年が、凄腕の大人達を派手に跳ばした。
親の跳ね満、親の役満と続き、ほどよく点棒を削った上で、とどめに親のトリプル役満を炸裂させた。
ちなみに少年と同卓にいたのは、
表プロとして最強決定戦の覇者となった雀士、
雀クマとして、関西を中心に荒らし回っているその筋では有名な打ち手、
もう一人は出雲組系の孫にあたる組から選ばれた代打ちの一人であった。
「片岡筆頭が強引に推薦枠にねじ込んだ、というのはあの子ですか。」
「ガキの負けは自分の負けでいいと大見得をきったらしいですぜ。
参加させないなら、自分は代打ちを降りるとそりゃあ駄々っ子みてえだったとか。
それにしても3コロたぁ、派手過ぎやせんかねぇ。」
「代打ち達が言うところの格付けでしょうね。」
白のブランドスーツをごく普通に着こなす、柔和な表情と穏やかな口調が同居する壮年の男、
出雲組組長にして、出雲組系全てのヤクザを束ねる総長、出雲和馬。
対極となる漆黒のスーツに身を包み、近づく者全てを威圧する雰囲気を醸し出しているのは、
出雲組系直系の12番、武闘派、極月組組長のドヤクザ、志藤尚道である。
年齢的には志藤の方が二回りは上であろうか。
「筆頭の引退するぞの脅し文句については、まぁいつものことですが.....
もしあの子供を後継者として出場させたなら、今度は本気かもしれませんね。
中学生の代打ち.....面白いじゃないですか。」
「あの爺さんの隠し子じゃぁねぇかって噂があちこちで流れてますぜ。
ガキの名前は岩倉小十朗......
ん?小十朗?総長、この名前.....どっかで......」
「私も少し気にかかったのですが.....
古株の志藤にもひっかかったとすれば、ハズレではないようですね。」
出雲和馬は心底楽しそうにモニターに映る少年を見つめている。
いや、少年の面影を通して、別の誰かを思いだしているのかもしれない。
「片岡筆頭は一筋縄ではいかないお方ですからね。
志藤、誰か人を使ってあの少年の素性と関係者を早急に調べあげなさい。」
「承知しやした。
でも総長、もしあのガキ、いやあの坊主が、いや、あの坊ちゃんがあっしらの想像通りだとするってーと」
「それはそれで構いません。
わかったことは随時、私に直接持ってくるように。
それと、ついでに弁護士先生を呼んできてください。必要になるかもしれませんから。」
岩倉小十朗、後に20年に及ぶ無敗伝説の幕はあがった。
しかし、少年の運命は木の葉が急流に流されるがごとく翻弄されることとなる。
「勝」つことで訪れた必然の別れ
「負」けることで得た絶ちがたい絆
勝負の行く末に待ち受ける運命とは―
次回 小十朗伝『代打ち〜南局〜』乞うご期待