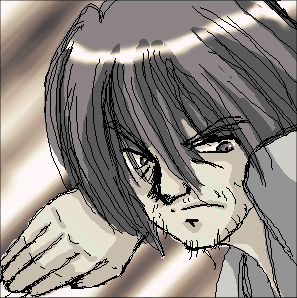
小十朗伝
『代打ち〜南局〜』
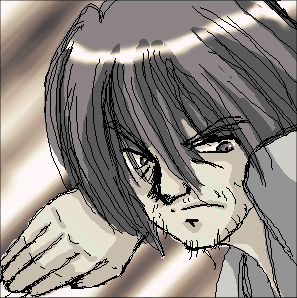
おむすび(鮭
小十朗は思春期まっただなかの中学生である。
その傍らには、ボイーンでキュでバイーンの、プロポーションがしっかりくっきりとわかるイブニングドレスの妖艶な人、
スラリと伸びた長身は、ファッション雑誌のモデルと言われても、納得の完璧さ兼ね添えた、美しさ。
つい先ほど、準決勝を小十朗と同卓で戦い終えたばかりの、雨宮ユウキなる人物は、執拗に小十朗に迫ったりしているのである。
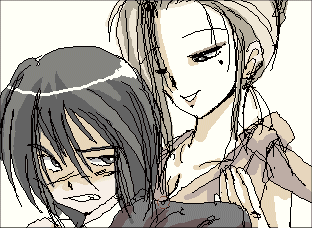
「もーちょっと、坊や待ちなさいってば。逃げなくったっていいじゃないのさぁ。心を許しあった仲じゃな〜い。」
「別に逃げてねーよ。脇腹をつつくな。許してねーし。」
ツカツカと早足で通路を進む小十朗に、ぴったりと寄り添う赤いドレスのユウキ。
「なぁに?じゃぁ、照れちゃってるのかなぁ?」
「照れてもいねーし。って寄ってくるな。近づくな。くっつくな。腕とるな。抱きつくなぁっ!」
「普段は年上ばっかりなんだけど、このくらい若いのもいいわぁ。
この大会終わったら一緒に暮らす?大丈夫、ちゃーんとおねーさまが食べさせてあげるからさぁ。」
「はぁ?」
「こーみえても料理は得意なの。ママ直伝一撃必殺陥落即席ニクジャガとか好き?」
「必殺の時点で食い物じゃねーし、馴れ馴れしくすんな。次で敵同士だろーが。」
「愛し合っていても立場がそれを許さないなんて、ロミオとジュリエットみたいよねぇ。」
「おい、おっさん。頼む。なんとかしてくれ。」
たまらず一緒に歩いている案内人のゴリラのような大男に助けを求める。
「こっちのたくましいお兄さんもいいわよねぇ。
はい名刺。坊やにはまだ早いけど、是非お店にいらしてねぇん。」
頼りになりそうな体格の割に、ユウキから名刺を受け取ると顔を赤らめてモジモジしたりしだした。全然当てにならない。
「たまたま利害関係が一致しただけだ。
それ以上でも以下でもねぇし、そもそも俺は肉じゃがよりカレーの方がって、あー鬱陶しい!」
「大丈夫大丈夫。カレーも得意よ。ママ直伝古今無双弱肉強食ボンカレー。ほら強そう。」
「...............誰か助けてくれ....」
準決勝は全自動の麻雀卓で行われた。
多くの人が、機械制御により賽の目や牌山が自動的に組まれる全自動雀卓では、イカサマはできないと思いこんでいる。
もちろんそれは大きな間違いである。
手積みのように自由にとはいかないまでも、実に様々な技が全自動においても存在、あるいは流用されている。
一般的に積み込み系の技は、自分が組んだ牌の山を有効利用するものである。
おおざっぱな利点として、あらかじめ上がりを仕込めるため得点が大きくできる。
しかし、全自動の場合は組まれる牌はランダムである。
ここで活用するべきは、テンパイスピード、つまり上がりの速度を速めることである。
そのためには対戦相手より早く、卓上の牌の情報を握り、かつ利用しなければならない。
既に捨てられている河から「拾って」きたり、
山の上段からツモる場合は、ほんの数瞬となりの牌をミリ単位でめくり、有効牌ならその場で「すり替え」。
通常1枚ずつしかつもれない牌を3枚「握りこんで」、逆に不要な牌を2枚おいてくる。
不要牌の処理は、相手に危険牌を送り込む方法としても有効である。
裏ドラをめくる際に、自分の思い通りの牌に入れ替える等々。
目の前で対戦相手となる3人もの監視者がいる中で、そんなことが可能なのかと問われれば、
不可能ではないという回答をせざるを得ない。
なぜなら麻雀というゲームの性質上、
1 自分の手牌に視線を落とす
2 自分のツモ牌に視線をやる
3 相手の捨て牌に視線を送る
この3つの動作は必ず必要であり、特に3は死活問題となる。
つまりイカサマを行うであろう相手を終始監視していられる人間は卓上に存在しないのである。
厳密に言えば1は盲牌で、2は記憶力で回避可能と思われるが、
牌の判別で指先へ神経を集中する、もしくは常に記憶の片隅にストックしておく余力は隙ができやすい。
これらに相方となる人物が同卓上にいる場合、コンビ技が加わりバリエーションは飛躍的に増えることも覚えておいていただきたい。
出雲組系雀王戦準決勝は東南戦、つまり半荘3回のトータル、勝ち抜けは上位2名である。
いずれも8グループにより行われた初戦を、ダントツトップで勝ちあがった猛者のみが残っている。
通常ならば、混戦が予想され、ギャラリーもその雀士達を対象とした賭事も大いに盛り上がるはずであった。
全自動卓とはいえ、一回戦のようなド派手な上がりが連発することが期待されていた。
しかし、初戦で超ド級の派手さで、にわかに注目を浴びた少年雀士・小十朗はごくごく地味な感じで、いとも簡単に勝ちあがった。
2位となった妙齢の美女と、仲良く得点を分け合った上で、イカサマらしい裏技を使うでもなくである。
会場にいた数名の雀士をのぞいて、このカラクリに気づけた者はおらず、
観客達は、派手な上がりを役満を期待していただけに、やや消化不良の感は否めない。
パーティ会場兼、巨大な賭博場に集う観客の注目は、早々と次の対局へと向けられた。
パーティ会場には、明らかに数名のガードとわかるヤクザが周辺をさりげなく警戒する一角がある。
出雲組の中でも、最重要の幹部達が無造作に集まっている。
全国的暴力団の巨頭会談級、組織のVIP達である。
「よくわからないのですが、つまり彼は何をしたのです?」
「ようするにあの坊やと、二位になった厚化粧の男とのコンビ打ちさね。」
白スーツの出雲組総長、出雲和馬の質問に答えたのは、地味な黒の留め袖を着こなした、そろそろ老婆といえる女性。
出雲組系の一つ、弥生組の代打ちをつとめる番堂梅である。
かつては麻雀小町の異名をとった、凄腕にして美しき女流雀士だった。
美しきのくだりを過去形で語らなければならないのは残念でならない。
そんな梅の解説を聞いて、総長の周囲にいた者達が騒然となる。
下戸で飲めない酒のかわりに、シュークリームを口一杯に頬張っていた極月組の組長、志藤尚道は、派手にクリームを噴き出したほどである。
「おいおいおい冗談だろ?どっから見ても女じゃねーか!」
たしかに小十朗と共に勝ちあがった人物は、顔つき、プロポーション、仕草のどれをとっても女性にしか見えない。
「極月のも、まだまだ男の修行が足りてないねぇ。」
梅は緑茶をズズズっとすすりながら、強面(こわもて)の志藤尚道をニヤニヤと見ている。
「彼女が彼かどうかはともかく、素人の私に、もう少しわかりやすく解説していただけませんか?」
「この手の技についちゃ筆頭の方が専門なんだけどねぇ、いないのかい?」
「何でも最後の仕掛けがあるとかで、席を外してます。」
「あの爺サマも、なに企んでるんだかねぇ。」
梅は、会場に設置されている巨大モニターとは別の、手元に置かれた小さなモニターで先ほどの対局を録画したものを巻き戻す。
「コンビ打ちというと、あの少年と彼女、いや彼ですか。二人に面識があったと?」
仮にお互いが顔見知りであったと不思議はない。
裏麻雀の世界は、世間が思うほど広い業界ではないのである。
公平性やルール違反といった言葉とは、無縁の卓上とはいえ、最初から二人対一人対一人で戦っていたというのであれば、
和馬の中で、いささか小十朗の評価を下げざるを得ない。
「いーや、元々組んでいたってのも、お互いが知り合いだったって可能性も低いね。
どちらかと言えば、あの場で顔見知りになったってことさ。この短い時間でできた急造コンビさね。」
梅の解説によると、1半荘の序盤、小十朗と便宜上「彼女」の間でサインの交換が行われている。
小十朗の捨て牌(河)の中に描かれた通しのサイン、
捨て牌の位置を微妙にずらして、自分の当たり牌を教えるというイカサマ行為に、彼女が答えたのである。
もちろん誰一人サインに気づかなければ、まったく無意味な行動であるし、
サインに気づいた者も、それを逆手にとって敵対関係を結ぶという場合もある。
しかし次に彼女が、小十朗の方法とは別のサインを出した時に、小十朗が同じように返答をしたのである。
二つ以上の複雑な通しを、無言のまま短時間で交換しあえた二人のもくろみは、利害関係の上で合意をみる。
この卓では、上位2名が勝ち抜けである。
サインの判らなかった対戦者の残り二人を、静かに、気づかれることなく、たたき落とせばいいのである。
先に述べたように、通し、いわゆる欲しい牌を気づかれずにサインで出し合うコンビ技が成立すると、
イカサマバリエーションの幅は、飛躍的に広がりをみせる。
上家と下家、いわゆる席が隣り合った場合には、卓の下で牌をやり取りするエレベーター。
対戦相手に危険牌をツモらせる送り込み。
協力関係にない他の二人より、2倍以上の早さで上がりへと向かうコンビ技は、非常に有効な手段となる。
しかし、仲間となる相手との連携と信頼が絶対条件であり、これを打ち合わせ無しのぶっつけ本番、
全く知らない人間と、即席でサインを組み上げるとなると、その技量は尋常ではない。
「麻雀を始めて3ヶ月で、そんなことまで出来るようになるものなんですか?」
「そんな簡単にできたら、あんた達も代打ち探しに奔走したりしないんじゃないのかい?」
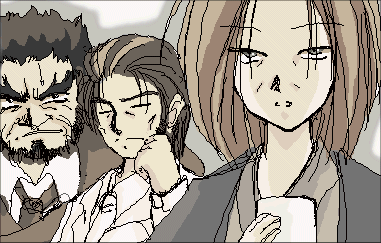
睦月、如月、弥生、卯月、皐月、鳴神、文月、葉月、長月、御忌、霜月、極月....
出雲を親の頂点として、12の子組で構成される出雲組系系列には、本来、各組ごとに一人の代打ちがいる。
しかし、実質仕事を任せられる代打ちの数は、筆頭の片岡重蔵や、現在解説を総長にせがまれている番堂梅を含めると7名に満たない。
なぜ麻雀というゲームを専門で扱う代打ちという存在が必要となるか?
その役割とは、相対する暴力団同士の利権を、戦争という手段を使わずにやりとりするためである。
利権を生むシマの取り合いに代表される暴力団の抗争は、しばしば数千人単位のドンパチに発展する。
そうなるとお互いの幹部から構成員、準構成員と呼ばれる兵隊、及び資金の消耗、
さらに警察の介入により、いらないところまで探られることを考えると、共倒れになる可能性が高い。
皮肉なことに、街の治安の維持することが、長い目でみれば悪党にとっても一番儲かるのである。
また、暴力団同士に限らず、一般の企業からの代打ちを依頼される場合も多々ある。
強力な打ち手を組織内に所属させておくことは、
出雲に限らず、様々な企業と裏から取引のあるヤクザという組織にとっては、必要不可欠な措置であるといえよう。
「準決勝は上位二名が勝ち抜けだ。
とはいえ、一人でも抜けだすのがいちゃ、残りの三人はそれを阻止に回る。
半荘の間に言葉を発するでも無し、視線を交わすでもなしで知らない相手と同盟を組むとは、本当に末恐ろしい子だよ。」
あの片岡重蔵が連れてきたのだから、ただの子供なワケがないというのはわかる。
しかし、少しばかり才能のありそうな子供に、
自分の麻雀を仕込んだというだけなら、わざわざこの場でお披露目をする必要があるのだろうか?
なにやら裏側で別の動きがある、梅の中に、わずかながらの疑惑が首をもたげ始める。
「ではもう一人の彼....雨宮ユウキさん。
彼の腕も相当なものだと考えていいんですか?」
本人のプロフィール用紙には、新宿は歌舞伎町二丁目にある店名と源氏名、さらにキスマークのおまけがついている。
最後に『みんなでお店にいらしてね〜ん』の後ろにキラキラしたハートマークが描き込まれてる徹底ぶり。
「いや、あくまで場を支配してたのは子供の方だね。
ただユウキってのかい?あれは自分が子供の方をコントロールした、と思わされてるだろうね。
次の決勝でも仲間だと思って油断してたら、骨までしゃぶり尽くされるのはオカマの方さね。」
「ひどいお話ですね。」
「そういう世界さね。」
カズマは改めて小十朗のプロフィールを確認する。
この準決勝の間に調べさせた彼の生い立ち、境遇、そして今現在、小十朗が暮らす白鳥園という孤児院が地上げの対象になっていること。
さらに、この地上げに関与しているのが、出雲組とは敵対関係にある黒曜会であることも添付されている。
白鳥園の建つ住所自体は、黒曜会のシマ内であり、この時代はどこの暴力団も旨味の大きい地上げには力を入れている。
おそらく大手の建設会社に依頼され、この周辺の住宅もろとも更地に戻し、利潤の高いマンションかビルの建設という流れのはずである。
これ自体は別段珍しいことでもなく、どこの街でも普通にある地上げの風景である。
しかし、もう一枚の資料はありふれたものではない、カズマが欲した情報が記されている。
出雲組の根底を揺るがすかもしれない、その事実をどう利用するか.......
小十朗を引っ張り込んだ片岡重蔵には、その絵図面ができあがっているはずである。
「総長。橋之下弁護士がいらっしゃいましたが、こちらにお通ししても?」
幹部周辺をガードする黒服の一人が、周囲に聞こえないよう、カズマに耳打ちをしてきた。
「いえ、別室でお会いしましょう。少々込み入った話になりそうですから。
決勝もそちらで拝見することにします。志藤、一緒にきなさい。
では、お梅さん。また後ほど解説をお願いしますね。」
パーティ会場では周囲の目も気にせずに、ユウキが小十朗を追いかけ回していた。
一見して女性ではあるが高身長のユウキと、小十朗の案内役となる2mを越す大男が会場を練り歩き、
その先頭には、本日の大会台風の目の少年が逃げ回ってるとなると、それだけで注目されてしまう。
ユウキの方は時折、周囲に営業スマイルを振りまきながら楽しそうではあるが、
小十朗にしてみれば、麻雀以外での苦労はごめん被りたいとこである。
「よし、わかった。
お互い決勝まで残ってるんだ、麻雀で勝負だ!」
とうとう会場のコーナーに追いつめられた小十朗は、周囲に宣言するように大声で叫んだ。
「何それ?熱血スポ根少年漫画?」
「俺が負けたら肉じゃがでもカレーでも喰う。
そのかわり俺が勝ったら二度と近づくな!」
「じゃぁ、私が勝ったら小十朗ちゃんを食べちゃっうってことでいいわね。」
蛇のように長い舌で真っ赤な唇をなめ回す仕草に、小十朗の本能的な危機を感じ取った。
「いや、え?俺が喰うんじゃないの???」
「まぁ、私は食べられるのも嫌いじゃないわよ?」
「とにかく麻雀で勝負だ!」
ドーンっと指差す小十朗に、ユウキはツツツっと近づいてくる。
「でもさ、さっきみたく次の決勝でも、邪魔な他の二人は蹴落としておきたくなぁい?お互いの為にもね。」
耳たぶに噛みつけるほどの至近距離、ユウキの囁きは、事の成り行きを見守っているギャラリーには聞こえていない。
「最初の東2でアタシがリード、東4で小十朗ちゃんも稼いで、南入りから改めて決着つけましょ。」
「あんたが裏切らないなら、それでもいいさ。」
「あたしの愛しい小十朗ちゃんを裏切るわけがないでしょ。バカね。」
小十朗の耳を軽く噛みながらの甘い囁き、その仕草とは裏腹に、ユウキの目は勝負士の輝きを放っていた。
その猛禽類の鋭さを持った瞳を、抱きつかれる形の小十朗は、見ることができなかった。
しかし、また同じくユウキも、小十朗の瞳に宿るそれを見ることはなかったのである。
出雲組系雀王戦決勝。
優勝すれば現金一千万円。さらに望めば特別卓での対戦。出雲系列での代打ちへの道が開かれる。
手積み卓による半荘一回勝負。
彼と彼女が手にするは栄光か、指の間をすべり落ちる無価値な砂粒か。
決勝の幕がまもなくあがるちょうどその頃、
小十朗の帰るべき場所、白鳥園は何者かの手によって炎に包まれていた。
帰るべき場所を失った少年。
信じるべき人を失った少年。
倒すべき相手を目の前にした時、少年は最後の選択を迫られる。
次回 小十朗伝『代打ち 〜オーラス〜』乞うご期待